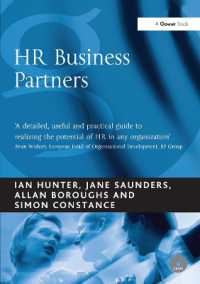内容説明
戦争とどう向き合い,受けとめるか──戦後,人々は直接的な体験の有無にかかわらず,戦争との距離をはかることによって自らのアイデンティティを確認し,主体を形成してきた.敗戦からの時間的経過や社会状況に応じて変容してゆく戦争についての語りの変遷をたどりながら,戦後日本社会の特質に迫る.解説・平野啓一郎.
目次
序 章 「戦後」後からの問い
1 問い直される戦争と戦後
「慰安婦」の告発と歴史修正主義/「戦後」後からの考察/シンポジウム「ナショナリズムと「慰安婦」問題」
2 戦後における戦争の語り
認識と叙述の推移/アジア・太平洋戦争の時間と空間
3 問われる戦争像
戦争認識研究の系譜/植民地認識の欠如/戦争像の考察
4 「戦争体験」から「戦争経験」へ
「経験」への着目/体験/証言/記憶の三位一体/帝国と植民地
第1章 「状況」としての戦争(一九三一―一九四五)
1 中国での戦争
満州事変/日中戦争/兵士たちの手記/映画の中の日中戦争/論評・文学の中の日中戦争
2 一二月八日の転換
新聞の中の一二月八日/小説の中の一二月八日/時間と空間の拡大/特派員たちの記す戦争/四つの『大東亜戦史』/構築される「大東亜戦史」/映画の中のアジア・太平洋戦争/戦争記述の三つの「型」
第2章 「体験」としての戦争(一九四五―一九六五)
1 「体験」としての戦記
戦記の出現/占領者たちの戦争像/戦記における時間と空間/参謀の戦記――インパール作戦?/「戦後」からの批判的再構成――インパール作戦?/アメリカの影――沖縄戦/微分化される「戦闘」
2 「体験」としての「引揚げ」と「抑留」
帝国の中の「人流」/分裂する「家族」「日本人」/主題化される「性」/「他者」としての「避難民」/引揚げのヒエラルヒー/「抑留」の経験/隠蔽される帝国/「日本人」の分裂と統合
3 「公刊戦史」と「通史戦史」
「全体」への志向/作戦の連なりとしての戦史/非軍人による戦史の登場/子どものための戦史/アンソロジーによる全体叙述の試み/「戦後」から「戦時」を読む/戦中派の発言
4 帝国―植民地と銃後
帝国認識の切開/問い直される「日本近代」/女性たちの「戦時」の記述
5 歴史学の「太平洋戦争」
歴史学者による戦争通史/せめぎあう「事実」とイデオロギー
第3章 「証言」としての戦争(一九六五―一九九〇)
1 書き換えられる「戦記」
書き換えの四つの「型」/ずらされる強調点/拡大する強調点/あらたな文脈と認識の提示/焦点としての沖縄/書き換えにともなう対立と論争/「戦場」の証言/「銃後」の証言/「沖縄戦」の証言/「空襲」の証言/証言の収集/「いかに」伝えるか
2 あらたな「引揚げ」記,あらたな「抑留」記
「故郷」と「家族」への思い/「植民地二世」たちの「引揚げ」/「他者」としての朝鮮人/「抑留」のあらたな語り/香月泰男『私のシベリヤ』
3 あらたな世代の「証言」
アメリカと交差した戦記/検証される戦時の時間と空間/戦闘と戦場の記述
4 加害の戦争認識
中国での証言/第七三一部隊の解明/「銃後」への問いかけ/加害者としての証言/「証言」の時代と論争
5 「証言」の時代の歴史学
「証言」の時代に切り結ぶ戦争像/「証言」と「事実」/「証言」から「記憶」へ/「戦後歴史学」の成果/媒体のひろがり
第4章 「記憶」としての戦争(一九九〇―)
1 「記憶」の時代のはじまり
戦争の語り方と戦後思想/浮上する「記憶」
2 「記憶」の時代の戦記・戦争文学
戦争文学における焦点の推移/非経験者による戦争文学の登場
3 「記憶」の時代の帝国―植民地
継続する「引揚げ」/継続する「抑留」/「発見」される帝国―植民地/帝国の視点からの語り直し/体験/証言/記憶
おわりに
補 章
注
あとがき
岩波現代文庫版あとがき
解 説……………平野啓一郎
関連著作年表
用語リスト
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
CTC
岡本 正行
吉田よしこ
-
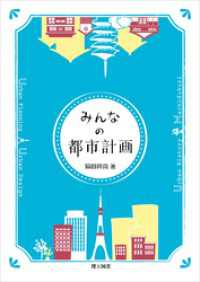
- 電子書籍
- みんなの都市計画