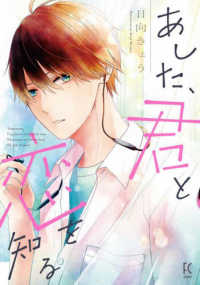内容説明
スマホ登場以来16年、教室にいるのはもはや私たちが知る「子ども」ではなくなっていた。ハイハイも体育座りもできない保育園児。教室の「圧」に怯える小学生。クラスメイトの姓すら知らない中学生。会ったその日にベッドインする高校生――児童に関する問題を丹念に追ってきた著者がデジタルネイティブの育ち方を徹底レポート。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きみたけ
89
考えさせる内容でした。著者は「こどもホスピスの奇跡」で新潮ドキュメント賞を受賞したルポライターの石井光太氏。保育園から高校まで200人以上の教師に取材を重ねた衝撃の現場報告。ハイハイも体育座りもできない保育園児、教室の「圧」に怯える小学生、クラスメイトの姓すら知らない中学生、会ったその日にベッドインする高校生など、児童に関する問題を丹念に追ってきた著者が、デジタルネイティブの育ち方をまとめた一冊。我が家の高2と中1の子供たちにもスマホを持たせていて、便利な反面、マイナス面もあるのは仕方ないなと感じてます。2025/03/08
Aya Murakami
85
図書館本。 スマホ育児(実はそれだけが原因ではない)を起点に小中高大と数々の問題が芋づる式にでてくる今の教育界をルポした本書。ハイハイができない、噛んで飲みこむ力がない、歩き方が怪しい…。絶句し、ゾッとしました。スマホと子どもの問題というと前頭前野の萎縮があげられますが、本書ではアタッチメントの問題の焦点を当てていますね。アタッチメント不足とほめ過ぎ育児が愛情飢餓とドーパミン漬けを引き起こすのだとか。Z世代より下の彼ら彼女らが社会に出てきたらどうなるのか心配です。2025/04/04
読特
80
物が散乱する狭い部屋にハイハイできない乳児。教室での人間関係のアツに保健室の予約が一杯になる小学校。浮くことの恐怖が上回り表彰されるのを怖がる中学生。不登校の増加で人気が高まる通信制高校。全入時代。一枚のプリントすら読めない大学生…現代の育児・教育環境の問題の断面を突き付ける。失われた30年を作ってしまった前の世代。発育環境や教育がよかったということにはならない。変化は歓迎すべきことだが、守るべきものは失わないようにしなければいけない。懸念を感じることは健全な心の現れ。信念を持った大人であり続けたい。2024/09/16
ムーミン
60
特に近年の幼児の実態には不安を感じました。都会の生活が子どもにとって良くないと、地方はまだまだ大丈夫だと思いたいです。2024/09/02
さぜん
52
デジタル•ネイティブの育ち方のレポート。保育園から高校までの教員200人以上の取材による報告が裏付ける事実に驚くと共に教育の重要さを改めて突きつけられる。98、00、02年うまれのウチの子達もどこかしら重なる点がある。自分の子育てを振り返ってその時代に影響されている点は否めない。教育の仕事に携わる人達の苦労や過酷さが想像以上だ。GIGA構想がタブレット配布やデジタル教科書導入が先走り、教育の本質が見失われていないだろうか?どこに解決策があるのか?子供は大人の姿を見ている。私達がまず襟を正さないといけない。2025/03/09
-

- 電子書籍
- 少年Aは嘲笑する 8 恋するソワレ
-
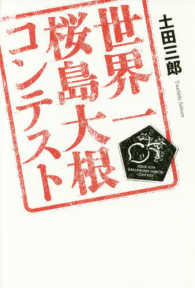
- 和書
- 世界一桜島大根コンテスト


![BBM広島東洋カープベースボールカードセット 〈2025〉 [トレカ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/45832/4583217943.jpg)