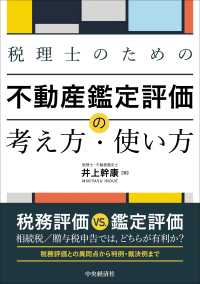内容説明
社会学の重要課題であった「社会秩序はいかにして可能か」という問いは二つの方向に分かれていった。秩序の成り立ちをめぐる精緻な分析はhowの問いに還元され、秩序のwhatを問う分析は他分野に委ねられた。しかし、本来はwhatとhowの切り分け難さこそが社会学の根底にある。本書は理論的な構想力からたどり着きうる秩序の条件を描き出す。
目次
序 「社会学の根本問題」と社会問題の社会学─whatとhowのあいだ
第I部 過去制作の方法──出来事の構築
第1章 存在忘却?──二つの構築主義をめぐって
補論 ジェンダーと構築主義
第2章 「構築されざるもの」の権利?──歴史的構築主義と実在論
第3章 構築主義と実在論の奇妙な結婚──ジョン・サール『社会的現実の構成』を読む
第4章 歴史的因果の構築──ウェーバーとポパーの歴史方法論を中心に
第II部 倫理制作の方法──責任と自由の構築
第5章 行為の責任を創り上げる──シュッツ動機論からルーマンの道徳理論への展開
第6章 「自由な人格」の制作方法──ウェーバーによる定言命法の仮言命法化
第7章 人間本性の構築主義と文化左翼のプロジェクト──ローティとともにローティに抗う
第III部 社会制作の方法──ルーマンをめぐって
第8章 他者論のルーマン
第9章 社会の討議──社会的装置としての熟議
第10章 社会の人権──基本的人権とは社会システムにとってなにか
あとがき
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぷほは
4
3部構成で構築主義再検討の1部とルーマン論の3部の間に両者を分析哲学や政治哲学を押さえた上で繋ぐ2部がある。初出から20年程の開きがあり、一冊のパッケージとしては微妙だが、例えば1部は昨今流行りの?「思弁的実在論」との比較が楽しめるし、そこが退屈でも2部7章のローティ批判の切れ味は抜群だった。私が一番勉強になったのはやはり3部なのだが、「社会資本や人的資本から疎外された弱者は、不作法な異議申し立てにすら、動機づけられない可能性がある。」(296)といった指摘があるからこの人は信用できるみたいな感じはある。2018/12/01
takao
3
ふむ2023/07/21
人生ゴルディアス
2
序盤はまだしもだった。社会学をやる際の「社会問題」を社会学者が任意に形成しては客観性がないからどうにかしよう、という方法論をめぐる苦闘だと理解できる。けど、言葉の指示する対象の実在云々とか、ローティという哲学者からの批判に対する反論でげんなりした。この哲学者は、ソーカルと同じように、我々の言葉を使って好き勝手やるな、と言いたかったんだろうが、それに対する著者の反論は、お前が間違っていると指摘する事実はあくまでお前が主張しているだけで我々には何の関係もない、だからお前の主張は成立しない、だ。マジかよって思う2019/02/05
pankashi
0
去年読書会で途中まで読んでいた残りを読んだ。勉強になるなあと思いつつ、再読しないと書いてあること全然わからんなあとも素直に思う(脱字が多すぎませんか?)(編集の人の苦労がしのばれる)2020/07/01
chiro
0
社会は社会を創る。その社会の実体は何なのか?社会の構成員とは誰なのか?かつては、わかりやすい意味での国家があり、特に単一民族という幻想下での我国にとっては共通認識を持ちやすかった。しかし、グローバル化の拡がりはこの問題を定義付ける事を難しくした。結果として、包摂だけでなく、排除という概念も社会を創るにあたっては考慮しなくてはならなくなった。そうなった時に基本的人権とはどう整合性をとるのか?数多の学者の主張から読み取れる可能性を示す事で選択の方法を考える助けを与えてくれた。2019/05/02
-

- 電子書籍
- 身代わり妻は悪魔の囁きにかき乱される【…