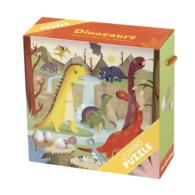- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
○博覧強記の金融ジャーナリストが膨大な文献を渉猟し、古代バビロニアから、中・近世ヨーロッパ、現代の日本、アメリカ、欧州、中国にいたるまで、金利の歴史絵巻を豊富なエピソードでカラフルに描き出す。そして、21世紀の超低金利時代における金利の本質、金融政策の有効性を問い直す。歴史を通じて現代を問う骨太で出色の読み物。
○金利とは何か? 利子は正しいものか? 適正な金利の水準とは? 何が金利の水準を決めるのか? 金利と経済成長の関係は? 「時間の価格」ととらえるのが最も妥当である金利は、生産、消費、投資、為替レートなどあらゆる経済の動きにかかわる。
○だが、歴史上、そして現代においても、金利は幾度も大きく低下し、そのたびに経済は不安定化し、乱気流に呑み込まれてきた。1920年代の大恐慌、1980年代の日本のバブル、2008年の世界金融危機はその悲惨な典型だ。そして、中央銀行の物価安定政策のもとで、主要国の金利は歴史上かつてないほど沈み込んできた。適切な金利がなければ、生産、貯蓄、投資すべての経済行動の価値を計るモノサシを失うことになる。資本主義経済は市場が定める金利がなくても繁栄することができるのか?
〇本書は、極端な低金利は資産価格インフレをもたらすだけでなく、経済成長率の低下、不平等の高まり、債務の累積、年金危機、不動産・資産バブルなど、経済全体にいかにダメージを及ぼすかを明らかにする。著者は、中央銀行による低金利政策はその意図とは逆にかえって経済を損ない、「隷従への新たな道」につながると警鐘を鳴らす。
目次
序 章 アナーキストと資本主義者
第I部 金利の歴史
第1章 生まれはバビロニア
第2章 時間を売る
第3章 利子の引き下げ
第4章 キメラ
第5章 ジョン・ブルは二%に耐えられない
第6章 気付けの一杯
第II部 低金利はさらに低い金利をもたらす
第7章 グッドハートの法則
第8章 長期停滞
第9章 バーゼルの鴉
第10章 不自然淘汰
第11章 発起人の利得
第12章 大きく、膨らんだ、醜いバブル
第13章 あなたのお母さんは亡くならなくてはいけません
第14章 信用を食べてはいかが
第15章 不安の対価
第16章 錆びつく貨幣
第III部 ビー玉ゲーム
第17章 諸悪の根源
第18章 金融抑圧と中国的特色
終 章 隷従への新たな道
追 記 さかさまの世界
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
koji
きみどり
こだまやま
どうろじ
-

- 電子書籍
- とめはねっ! 鈴里高校書道部(8) ヤ…
-
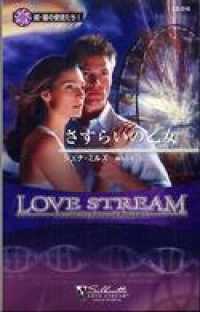
- 電子書籍
- さすらいの乙女 続・闇の使徒たち I …