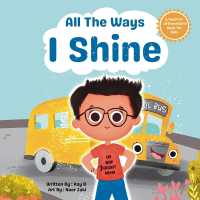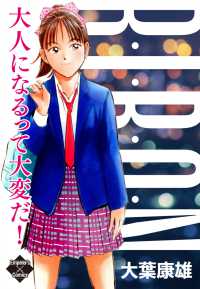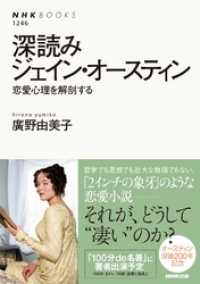- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
戦後日本を代表する知識人・鶴見俊輔は,民主主義と平和主義を社会に根づかせる積極的な役割を果たした人と目されながら,一方でそれらに対する懐疑を抱き続けていた.日常性に根ざす思考に可能性を見いだし,「新しい知」のあり方を模索し続けた鶴見が,彼方に見ていたものは何だったのか.その豊饒なる思想世界の解読に,「いのち」をめぐって問いを積み重ねてきた著者が挑む.
目次
はしがき
序章 正義と狂気のあいだ
思想家と二つの顔
「春子」と「退行計画」
政治と文学
ハウスキーパーと日本共産党
「反・反共」と「反共」と
本書の主題
I 反戦の思想と行動
第一章 一九六九年八月・大阪城公園
1 「反博」とベ平連の危機
ベ平連の二重構造と「反博」
声なき声の会とベ平連
2 市民と土民のあいだ
「土民」対「市民」
石川三四郎の「土民生活」とデモクラシー
「市民」という幻想
3 市民運動家としての資質
鶴見と小田との不和
悪人と善人と
I am wrong
方法としてのアンビヴァレンス
4 徳永進と「らいの家」
「反博」のなかの「らいの家」
戦争が〈らい〉を解放する
戦争とハンセン病
ベ平連に対する違和感
第二章 大東亜共栄圏とハンセン病
1 鶴見俊輔とハンセン病
書かれざるハンセン病
大江満雄とハンセン病
ハンセン病問題の核心
ハンセン病の哲学
2 ライはアジアを結ぶ
アジアとハンセン病
戦中期の大江満雄──『辻詩集』
『大東亜』からアジアへ
大江満雄の戦後
鶴見と大東亜共栄圏
3 竹内好とアジア
一二月八日の感泣
アジア主義の戦後
竹内好と大東亜共栄圏
4 「交流の家」再考
戦後の「大東亜共栄圏」構想
癩者から来者へ
第三章 反戦と好戦のあいだ
1 開高健とベトナム人民
ベトナム人民とは誰か
民族自決主義のジレンマ
ベトナム戦争とは何だったのか
ベ平連解散の謎
2 戦争という愉楽
ページェントとしての戦争
開高健への共感
古山高麗雄の「反戦屋」批判
崇高にしておぞましき戦争
反戦の根拠
3 従軍慰安婦のアポリア
娼婦と慰安婦
アジア女性基金
選言命題と老年
無能力としての能力
おわりに
II 新しい知を求めて
第四章 民族主義のパラドックス
1 葦津珍彦と「非国家神道」
葦津珍彦との出会い
葦津珍彦への評価
日本的思想と日常的思想
国家神道と非国家神道
2 『夢野久作』と天皇のイメージ
一木一草の天皇制
天皇と銭湯
ドグラ・マグラの世界
ドグラ・マグラとベ平連
夢野久作と杉山泰道
3 天皇とアナキズム
ラディカル・デモクラシーとアナキズム
外典としての夢野久作
葦津珍彦のアナキズム
石川三四郎と天皇
第五章 戦後民主主義のルーツ
1 『アメノウズメ伝』への視座
石川三四郎の『古事記』研究
アメノウズメと一条さゆり
犯される側の論理
『アメノウズメ伝』と明石順三
科学と神話
2 漫才とディスコミュニケーション
『太夫才蔵伝』と大衆芸術
外来思想と伝統思想
半身性の文化
デューイ批判とディスコミュニケーション
ディスコミュニケーションとしての民主主義
3 「準国家」と戦後民主主義
デューイと民主主義
共同体への関心
「準国家」からの展望
コミュニティとアソシエーションのあいだ
第六章 ローカルな普遍性
1 『思想の科学』を越えるもの
「うち」と「おたく」
サークル文化としての『思想の科学』
『思想の科学』の原点
『思想の科学』へのアンチテーゼ
反国家、反アカデミズムの志
2 プラグマティズムの「学びほぐし」
出発点としての『アメリカ哲学』
『アメリカの革命』から『北米体験再考』へ
プラグマティズムの源流
インディアンとアルバニー連合計画
黒人解放運動とプラグマティズム
良行の失望感
3 アカデミズムと民間学
一九六九年ふたたび
大学闘争と学問の危機
「日本発」という理念
『民間学事典』のジレンマ
「女、子ども」とは誰か
「ぬるい感じ」と高き志
むすびに代えて
資料 鶴見俊輔の石川三四郎宛書簡三通
参考文献
あとがき
人名一覧
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
踊る猫
Go Extreme
tu-ta