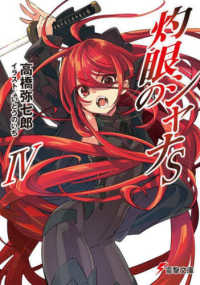内容説明
ロマンあふれるイメージが強い古生物学だが、その研究現場は苦悩の連続だ。40億年に及ぶ地球環境や生命進化の歴史を明らかにすべく、化石を手がかりにして、今は絶滅してしまった古生物の生態や地球環境の変動の歴史までを紐解こうとするが、バイアスだらけ、わからないことだらけ。化石は過去に地球に生息していた古生物の遺骸や痕跡が地層の中に残されたもの。長い年月を経て変形していることもあるし、化石が完全体であることはほとんどない。そこで、古生物学者は化石や地層に刻まれた情報からだけでなく、現在の生物を観察したり、数理モデルを駆使したり、様々なアプローチも用いて研究に挑んでいる。何億年も前の世界に思いを馳せながら一歩一歩進む学問の世界を気鋭の古生物学者が描き出す!! 【目次】第一章 古生物学とは/第二章 地層から古生物学的な情報を読み解く難しさ/第三章 古生物学の基礎知識/第四章 化石から「わかること」とは……?/第五章 化石を研究しない古生物学者/第六章 古生物学の研究はブルーオーシャン/あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bapaksejahtera
15
化石研究を中心とする本分野は、一般にロマンに満ちた研究分野とされるが、研究者の少なさにも関わらず、研究対象は動植物全体に及ぶと共に、その生息環境の把握に欠かせない地質変化の分析は必須である。更に研究者の殆どは地球科学を学問背景にするが、生物系の学問も身に着けなければならない。数理モデルや放射線崩壊や同位体等原子核構造と変化の知識も必要である。化石は過去の生物体内の軟組織が何らかの条件で鉱物に置換した物であるから学問対象は、古生物体系のごく一部を占めるに過ぎない。本書は真面目な学者が自他に啓発を試みた物。2024/11/18
大先生
13
後半は、ちくまプリマー新書にしては難しめの内容でした。古生物学の世界は、まだまだ分からないことだらけでブルーオーシャンだから君も古生物学者にならないか?という趣旨のようですが、それならもう少し簡単な内容にしておけばいいのに。バイアスという問題がたくさんあるというのも隠しておけばいいのに(笑)著者はきっと正直者なんでしょうね。軟組織やうんちの化石の話は面白かったのですが。2025/12/25
nagata
9
古生物学と仕切り直して専門的な話がどばーっと展開されるのかと思いきや、普通の人目線からの化石や地層を解きほぐしつつ、それらが学問的に評価されるに堪えうるには様々な検討や仮説検証を経ていることが研究者目線で書かれる。どちらからも一人称的な語り口で、内容は決して易しくないものの、何故だか腑に落ちる。これまでの生物が現地球の地層内に化石として残存する割合の推定などを示されると、それだけ希少なものだけに頼らず、とはいえ当てればデカい。それだけでもロマンを感じる。2025/08/29
竜王五代の人
9
古生物学というものが、遺骸というものがほとんど化石に残らないものである(たくさん化石になるようなら大変である)ことや、どこに転がっていくか分からないなど、かなり不安定な足元に立っていて、それでも仮定と新たな手法を重ねて研究をすすめて行こうと語る本。古生物学が不安になる。 2024/09/28
まるよし
8
本屋でビビッと来て即買い。間違ってなかった。古生物学に対する熱量があるので、どこが興味深いのか、どこまでわかってどこからわからないのかが、(現時点の理解で)紹介されている。ここから先は一緒に切り開いていきましょうという、扉を叩く準備運動のような書。漠然とした化石堀のイメージから、ロジカルな印象に変化しました。2024/06/22
-
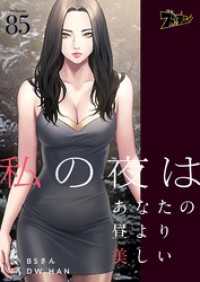
- 電子書籍
- 私の夜はあなたの昼より美しい【タテヨミ…