- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
習い事や家族旅行は贅沢?
子どもたちから何が奪われているのか?
この社会で連鎖する「もうひとつの貧困」の実態とは?
日本初の全国調査が明かす「体験ゼロ」の衝撃!
【本書のおもな内容】
●低所得家庭の子どもの約3人に1人が「体験ゼロ」
●小4までは「学習」より「体験」
●体験は贅沢品か? 必需品か?
●「サッカーがしたい」「うちは無理だよね」
●なぜ体験をあきらめなければいけないのか
●人気の水泳と音楽で生じる格差
●近所のお祭りにすら格差がある
●障害児や外国ルーツを持つ家庭が直面する壁
●子どもは親の苦しみを想像する
●体験は想像力と選択肢の幅を広げる
「昨年の夏、あるシングルマザーの方から、こんなお話を聞いた。
息子が突然正座になって、泣きながら「サッカーがしたいです」と言ったんです。
それは、まだ小学生の一人息子が、幼いなりに自分の家庭の状況を理解し、ようやく口にできた願いだった。たった一人で悩んだ末、正座をして、涙を流しながら。私が本書で考えたい「体験格差」というテーマが、この場面に凝縮しているように思える。
(中略)
私たちが暮らす日本社会には、様々なスポーツや文化的な活動、休日の旅行や楽しいアクティビティなど、子どもの成長に大きな影響を与え得る多種多様な「体験」を、「したいと思えば自由にできる(させてもらえる)子どもたち」と、「したいと思ってもできない(させてもらえない)子どもたち」がいる。そこには明らかに大きな「格差」がある。
その格差は、直接的には「生まれ」に、特に親の経済的な状況に関係している。年齢を重ねるにつれ、大人に近づくにつれ、低所得家庭の子どもたちは、してみたいと思ったこと、やってみたいと思ったことを、そのまままっすぐには言えなくなっていく。
私たちは、数多くの子どもたちが直面してきたこうした「体験」の格差について、どれほど真剣に考えてきただろうか。「サッカーがしたいです」と声をしぼり出す子どもたちの姿を、どれくらい想像し、理解し、対策を考え、実行してきただろうか。」――「はじめに」より
目次
■はじめに
子どもの必需品とは何か/見過ごされてきた「体験格差」/本書の構成
■第一部 体験格差の実態
「体験」がなぜ重要なのか/小4までは「学習」より「体験」/初の「体験格差」全国調査/体験は贅沢品か
1.「お金」と体験格差
「体験ゼロ」の子どもたち/体験にかかる値段/体験の「提供者」ごとの違い/体験をあきらめさせるもの
2.「放課後」の体験格差
スポーツ系でも文化系でも/人気の水泳と音楽で生じる格差/子ども目線で「放課後」を考える
3.「休日」の体験格差
自然体験も居住地よりお金/旅行の格差/近所のお祭りにすらある格差/「楽しい思い出」があることの意味
4.「地域」と体験格差
都市部と地方の体験格差/より細かく「地域」を見ていくと
5.「親」の体験格差
「親の体験」と「子どもの体験」/「あきらめさせた」と感じる背景
6.体験格差の「現在地」から
「無理をする」か「あきらめる」か「求めない」か/「現在地」の先へ
■第二部 それぞれの体験格差
事例1:サッカーがしたいです/子どもは親の苦しみを想像する
1.ひとり親家庭の子ども
事例2:体験は後回しに/事例3:最低賃金で働く/事例4:自転車も買えない/貧困と孤立の中を生きる親子
2.私が子どもだった頃
事例5:泣きながらやったピアノ/事例6:アウトドア系は行ったことがない/過去と現在、未来
3.マイノリティの子ども
事例7:障害のある子を育てる/事例8:ほかの子にできることができない/事例9:5人の子と海や山には行けない/選択肢が狭まっていく要因/体験の場をより包摂的に
4.体験の少ない子ども時代の意味
事例10:子どもの頃は買えなかったピアノ/子どもたちから何が奪われているのか
■第三部 体験格差に抗う
1.社会で体験を支える
体験の優先されづらさ/5つの提案/子どもへの経済支援/体験と子どもをつなぐ/体験の場を支える
2.誰が体験を担うのか
小さな担い手たち/自分の暮らす地域で
■おわりに
■参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あすなろ@no book, no life.
たかこ
yunyon
ミキ
レモン
-

- 電子書籍
- メガロザリア【分冊版】 5 青騎士コミ…
-
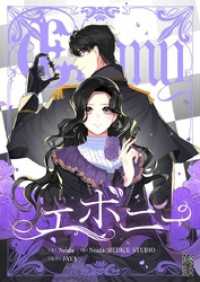
- 電子書籍
- エボニー【タテヨミ】第42話 picc…
-
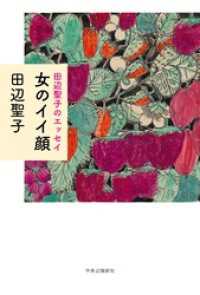
- 電子書籍
- 田辺聖子のエッセイ 女のイイ顔
-
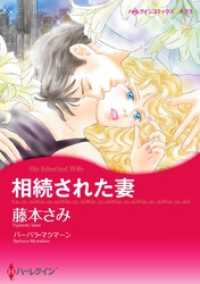
- 電子書籍
- 相続された妻【分冊】 10巻 ハーレク…
-

- 電子書籍
- 週プレNo.11 3/16号 週プレ




