内容説明
人々は読書という行為にいかなる期待を込め、そしてその期待はいかなる社会的背景で形作られたのか。1930年代、1980年代の中国を対象に「いかに読むか」に対する論争を歴史的に分析する本書は、過去からつながる現在の中国を理解するとともに、これからの読書を考えるものである。
【主要目次】
序章 焚書の政治から読書の政治へ――書物をめぐるシンボリズム
第1章 上海の「グーテンベルクの銀河系」――先行研究・視座・時期設定
第2章 消費する読者への交錯する期待――読書雑誌とその機能
第3章 民族を引き上げる読書――国民党の文化運動
第4章 行動のための読者――左翼にとっての抗戦
第5章 革命的な読書――連続性のなかの毛沢東時代
第6章 読書熱の両義性――ポスト文革へのあゆみ
第7章 未完の「八十年代」――『読書』時代の終焉
終章 読書の政治学
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
BLACK無糖好き
19
近現代中国における読書規範を分析し、その連続性と断絶を明らかにする。読書を主題とする雑誌を資料として用い、民国期から人民共和国期、文革をへて改革開放へと時代が変わる時々において、「あるべき読書」とはどのように定義されてきたのかを考察している。教養を深めるための「教養的読書観」や政治目的のための「道具的読書観」の対立など、エリートと大衆においても読書に対しての向き合い方には立場の違いもある。◆読書に関して、個人的には読書規範で領導されるより読書の自由を重視したい。読書の自由は思想の自由でもある。2025/04/19
TK
0
「本を焼く者は、やがて人も焼くようになる」というハイネのことばの引用から始まるカッコ良い本。1930年代以降の中国における「あるべき読書」をめぐる論争を、①読書から利益を得るのは集団(民族・国家)か個人か、②読書の効果は即時的なのか遅延的なのか、という二つの対立軸を持つ四象限の移動としてまとめている。単純化しすぎという感はもちろんあるが、それを補って余りある鋭い分析力を時代による読書規範の変化に対して示した本という印象。2025/06/08
オオタコウイチロウ
0
『生活教育』・『戦時教育』の周辺、つまりは陶行知生活教育派が、なぜ延安へとも接続されてゆくのか、という点でも参考になった。第4章。2024/12/06
-

- 電子書籍
- 木洩れ日のひと【単話】(7) FEEL…
-
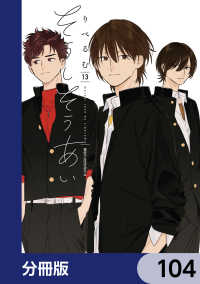
- 電子書籍
- そうしそうあい【分冊版】 104 MF…
-

- 洋書電子書籍
- 最新センサー・ハンドブック(第5版)<…
-
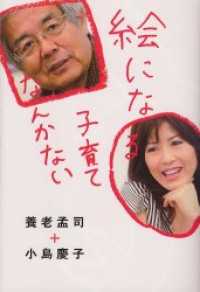
- 電子書籍
- 絵になる子育てなんかない 幻冬舎文庫
-
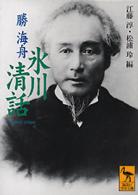
- 和書
- 氷川清話 講談社学術文庫




