内容説明
ヒトは働かずにはいられない!
ヨーロッパ中心の労働史観に風穴を開ける、人類始まって以来の労働の世界史。
すべての時代において、常に家庭が仕事の基盤にあった。家事労働に始まる仕事の歴史は小さなコミュニティから大きなコミュニティへと社会的な労働へと発展した。私たちにとって仕事とは何か、仕事に見出す人生の意味、協力する喜び、そして公平性への希求は、狩猟採集時代から私たちのDNAに組み込まれている。
私たちが仕事から解放されるユートピアは、ほんとうに私たちを幸せにするのか? これからの働き方を考えるための必読書。
【内容】
序章
第1部 人間と仕事~70万年前から1万2000年前まで
第1章~第3章
第2部 農業と分業~紀元前1万年から紀元前5000年まで
第4章~第7章
第3部 新しい労働関係の出現~紀元前5000年から紀元前500年まで
第8章~第10章
第4部 市場に向けての仕事~紀元前500年から紀元後1500年まで
第11章~第15章
第5部 労働関係のグローバル化~西暦1500年から1800年まで
第16章~第17章
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
りょうみや
25
著者は労働史専門の歴史学者。狩猟採集社会から始まるのでサピエンス全史と似た雰囲気がある。(認知革命や虚構はない。)そして古代から近代まで世界中の文明の具体例が取り上げられていく。分業、階層化、貨幣、市場、奴隷がこの巻のキーワードになるだろうか。人間関係、ジェンダーが裏テーマ。正直理解不十分だけど続けて下巻を読んでみることにする。2024/06/01
Mc6ρ助
17
『銅生産は十八世紀に排水の問題から縮小を余儀なくされた。幕府が賃金を引き下げたせいで、水抜き作業をする労働者が鉱山に来なくなった・・かわりに罪人やごろつき・・周辺の村の百姓・・都市の無宿者まで動員された。・・労働者に、事業者が米を特別な価格で独占販売するという強制現物給与・・労働者の数が多いほど事業主の店の儲けがそれだけ大きくなり、それゆえに省力技術を導入するうまみはなかったのだ。・・自由労働市場を放棄した結果、労働集約型生産の改善も進まなかった。(p362)』新自由主義経済恐るべし。歴史は繰り返すのか。2025/03/11
佐藤一臣
4
ヒトの労働の変遷をかなり細かいところまでたどっていきます。あまりに細かいので、ちょっと論が散漫かな?というよりも一直線で労働観が変化しているわけではないので、こんなふうに前後左右にぶれているのが労働の歴史らしい。読んでいて、労働観の変化のカギは「都市化、遊牧民、磨製石器、火起こし、言語、気候変動、乱獲、人口増、出産間隔の短縮、神話宗教、再分配、貨幣、奴隷、軍人、植民地、船員、ギルド、副業」あたりか?実は中世の人は保険保障、副業、賃労働をかなりやっていたんですね2024/08/21
yes5&3
0
240511日経書評。人間の活動力を労働、仕事、活動に分類したハンナアレント「人間の条件」読後に。人類の歴史で発生した様々な文明における「労働」。この本の見方をすれば、高付加価値を生み出して莫大な報酬とか、家庭内労働の賃金換算とか、もっと言えば●●時間の労働で●●時間余暇、というのは、人類史のごく最近の特殊な環境下の特殊な物差しに過ぎないと思わせる。賃金労働は四千年前に存在していても一時衰退したこともある。著者は、理想の制度を提示するのではなく、労働の在り方は様々なのだ、と伝えたいのだ、と感じつつ下巻へ2024/10/24
YASU
0
本書冒頭に触れられているがWorkの定義はとても難しく、人間の活動のうち“労働ではない”ものの規定さえ明確ではないのである。それを踏まえたうえで、本書は労働を関係性から「互酬、貢納―再分配、奴隷労働、賃金労働、自由労働」に分け、その具体的な変遷を各文明・時代ごとに叙述していく。そこから見えてくるのは、古典的唯物史観的な生産関係の単純な発展図ではない。詳細な分析によってはじめて生き生きと描写できる、様々な生きた人々の姿である。したがって歴史貫通的な普遍モデルを求めて読んでも期待外れに終わるだろう。2024/07/06
-
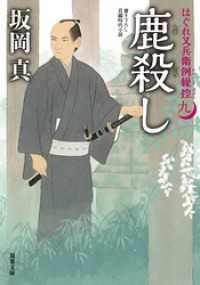
- 電子書籍
- はぐれ又兵衛例繰控 : 9 鹿殺し 双…
-
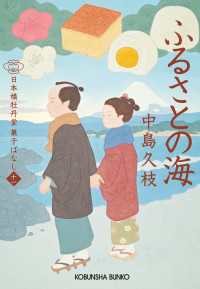
- 電子書籍
- ふるさとの海~日本橋牡丹堂 菓子ばなし…
-
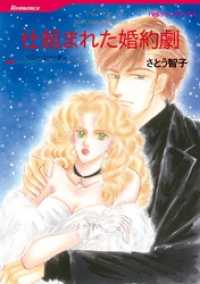
- 電子書籍
- 仕組まれた婚約劇【分冊】 12巻 ハー…
-
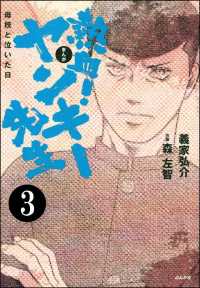
- 電子書籍
- 熱血!ヤンキー先生 母校と泣いた日(分…
-
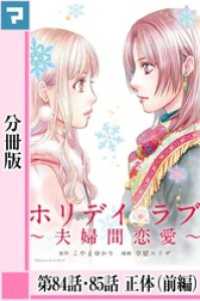
- 電子書籍
- ホリデイラブ ~夫婦間恋愛~【分冊版】…




