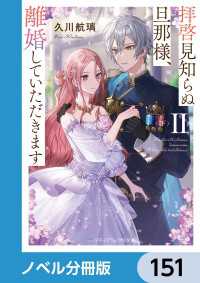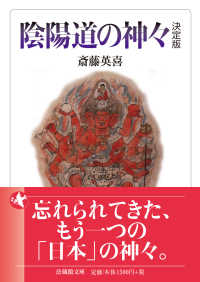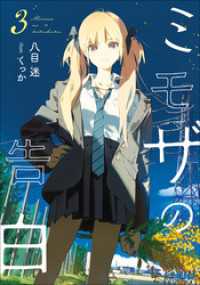内容説明
コミュニケーション観の探究が社会全体を見る鍵となるのは、なぜか?──
「コミュニケーション論のまなざし」は、個人や社会をどのように捉えようとしているのか。社会で言われていること、コミュニケーションを通して為されていることを、この「まなざし」はどのように捉えるのか。どのようにして、コミュニケーションは、単なる情報伝達ではなく、歴史、文化、社会の中で起こる出来事だということを、この「まなざし」は示していくのだろうか。
[目次]
1. コミュニケーション論のまなざし 1
まなざし(1) 大学で学ぶということ 1
まなざし(2) コミュニケーション論の地平 11
2. コミュニケーション論のための言語学の「知の枠組み」
「言語学」を具体例として見る学問の構成のされ方 31
枠組み(1) コミュニケーション論と心理学、メタ語用論、そして言語学へ 31
枠組み(2) 言語学とは何か:導入 37
枠組み(3) 語用論とは何か 44
枠組み(4) 文化的意味範疇とは何か 53
枠組み(5) 文化的意味範疇とコミュニケーション 59
枠組み(6) 語用論の世界:直示(ダイクシス)と視点 67
枠組み(7) 言語と方言 79
枠組み(8) 言語の全体:コミュニケーション、方言、言語構造、普遍文法 88
枠組み(9) 言語構造の構成と言語変化 104
枠組み(10) 言語の全体への〈まなざし〉としての言語学:総括 119
3. コミュニケーション論の「知の回路」
コミュニケーション・モデルと言語学とをつなぐ 129
回路(1) コミュニケーションの3つのモデル:視点とメタ語用 129
回路(2) 情報伝達モデル 131
回路(3) 6機能モデル 141
回路(4) 出来事モデル 162
回路(5) 出来事の視点から見た文法、意味論、語用論:コミュニケーション出来事と普遍文法、再訪 174
回路(6) コミュニケーションと視点:参加者の視点、観察者の視点、相互行為の基点 182
回路(7) コミュニケーションの変容とオリゴ 188
回路(8) コミュニケーション空間の編成、オリゴの転移、主観と客観 192
回路(9) コミュニケーション論の視点/まなざし:結語 195
4. 知の枠組みと回路のための15冊 201
知の枠組みのための10冊 201
知の回路のための5冊 205
目次
[目次]
1. コミュニケーション論のまなざし 1
まなざし(1) 大学で学ぶということ 1
高校にはない科目 1
専門的で総合的 3
抽象性と具体性/理論と経験 4
自己理解/自己分析 5
大学という「自由の空間」の意味 7
まなざし(2) コミュニケーション論の地平 11
学問の出発点 12
コミュニケーションを通して個人は創られる? 15
なぜ複数のコミュニケーション観が存在するのか? 19
自文化中心主義(エスノセントリズム)の危険性 21
なぜ理論化が必要か? 23
「養成ギブス」と「多角レンズ」への招待 25
練習問題 28
2. コミュニケーション論のための言語学の「知の枠組み」
「言語学」を具体例として見る学問の構成のされ方 31
枠組み(1) コミュニケーション論と心理学、メタ語用論、そして言語学へ 31
視点という問題=社会と心理を結びつける 31
喧嘩じゃなくて、じゃれあいだよ 33
じゃれあいが喧嘩に 34
枠組み(2) 言語学とは何か:導入 37
文法と言語使用(語用) 37
「意味をコード化する形式」 38
意味41
枠組み(3) 語用論とは何か 44
「意味」?―言及指示的意味と社会指標的意味 45
コンテクストが分からないと、意味が分からない 48
語用論と文法のちがい 50
枠組み(4) 文化的意味範疇とは何か 53
社会指標的な意味との結びつき 54
体系化の強弱と視点 57
枠組み(5) 文化的意味範疇とコミュニケーション 59
プロトタイプ 59
コンテクスト依存性が高い文化的意味範疇 63
コンテクスト依存性の高低 65
枠組み(6) 語用論の世界:直示(ダイクシス)と視点 67
「昨日」という言葉の意味は? 68
オリゴ(origo) 70
「システム・センテンス」と「テクスト・センテンス」 76
枠組み(7) 言語と方言 79
区別という難問 79
実際に使われる言葉は、すべて方言と考える 81
言語構造は、方言的差異の寄せ集めが体系化されたもの 83
語用共同体(speech community)と言語共同体(linguistic community)85
枠組み(8) 言語の全体:コミュニケーション、方言、言語構造、普遍文法 88
語彙と文法 90
象徴・指標・類像 92
指標性がコミュニケーションの基本的なモード 94
名詞句階層 97
語用論に投錨された4つの文法範疇 100
枠組み(9) 言語構造の構成と言語変化 104
音素は言語構造の入口 104
形態統語範疇 106
言語構造の構成原理 108
異音 109
複数の言及指示対象 111
語用論レベルでの変異が、なぜ語彙部に持ち込まれるのか 113
枠組み(10) 言語の全体への〈まなざし〉としての言語学:総括 119
統合性と象徴性 120
ほか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
マック