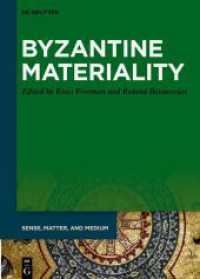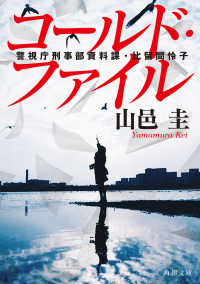内容説明
東京大学が「帝国大学」だった頃、すべては始まった――
「東大」出生の秘密を暴き、その虚像と実像を抉り出す!
*
明治19年の帝国大学の誕生は、のちの東京大学をも貫く基本性格を確立した歴史的特異点であった。エリート官僚養成、アカデミズムの独占的権威、立身出世・受験競争の頂点――伊藤博文、森有礼、井上毅ら設計者たちの政策的意図を辿りつつ、今日まで続く東大の本質とイメージの淵源を明らかに!
[目次]
第一章 帝国大学の出自――リヴァイアサンの生い立ち
第二章 帝国大学のモデル――ドイツの大学から学ばなかったこと
第三章 官庁エリートの供給源――工科系から法科系へ
第四章 出身と出世――上昇気流にのって
第五章 明治アカデミズムの体質――講座制と研究
第六章 もしも帝大がなかったら――批判的展望
あとがき
解説 科学史/大学史を超えた「学問の歴史」 石井洋二郎
目次
第一章 帝国大学の出自――リヴァイアサンの生い立ち
第二章 帝国大学のモデル――ドイツの大学から学ばなかったこと
第三章 官庁エリートの供給源――工科系から法科系へ
第四章 出身と出世――上昇気流にのって
第五章 明治アカデミズムの体質――講座制と研究
第六章 もしも帝大がなかったら――批判的展望
あとがき
解説 科学史/大学史を超えた「学問の歴史」 石井洋二郎
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえぽん
49
科学史家による帝国大学時代(明治19-30)を中心とした東大論。帝国との名称は権威があって響きがいいインペリアルの訳で帝国主義とは無関係とした点、模したと言われるドイツの大学とは修学・教授の自由がなかった点で全く異なっていた点、科挙的筆記試験は19世紀まで欧州で一般的でなかった点、卒業試験の成績で就職先や初任給まで差を付けていた点など、丹念な調査に基づく記述に感銘。頭と権力の分離をとの主張には賛同しかねるが、官僚養成機関の帝大を頂点とした構造が、各大学の百家争鳴を通じた学問創造を妨げたとの説は首肯できる。2024/07/30
穀雨
10
明治10年代から20年代の帝国大学(すなわち東京大学)草創期に光を当てることによって、諸外国と比較した日本の大学制度の成り立ちやその特質を浮き彫りにしている。「出世の嶺は八ヶ岳」とか「ブルジョア慶應、民権早稲田」とか、時折出てくる軽妙な言いまわしがおもしろい。あとがきにもあるように、著者は勤務校の東京大学で定年退職間際まで平講師どまりと冷遇されていたようだが、あくまで筆致は冷静で、それがかえって内容に説得力を与えている。2025/06/07
氷柱
6
1079作目。5月17日から。東京大学の歩んできた歴史が紐解かれた一作。国としてのスタイルの確立や各国からの文化輸入に一役買っていたというよりも、そういったものの集積が帝国大学の成立に関与していて、大学の成立はもはや必然的なものであったと言える。今の東京大学の姿は当時のものと大きく異なっていると思われるがそれでも日本にとって最重要視される大学であることに変わりはない。2024/05/20
inenoha
4
東京大学の黎明期,すなわち(旧)東京大学から帝国大学への移行期を中心に,この大学と他の省庁所管の高等教育機関(司法省法学校,工部大学校)との関係,理工科教育から法科教育への重点の移行,それにともなうドイツ語重視の傾向などを要領よくまとめている.2024/04/16