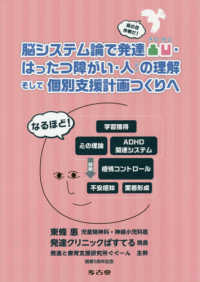内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
明治期にイギリスから持ち込まれ、岩手に根付いたホームスパン。羊毛を手紡ぎで糸にし、手織りで丁寧に仕上げていくスタイルは、県内各地の工房や作家らが大事に受け継いでいる。
軽くて暖かく、まとう人を優しく包む肌触りと、一本一本の糸が織りなす微妙で繊細な色合いは唯一無二のもの。親子3世代で着続けることができるその布は、「時を越える布」として今も多くの人たちに愛されている。
本書は〈つかう〉〈つくる〉〈しる〉〈ひろげる〉〈つたえる〉の5章を通じて、ホームスパンの魅力と奥深さを紹介。意欲作を次々と生み出す「つくり手」、製品をこよなく愛する「つかい手」、そして岩手に根付かせた先人と現在の「つなぎ手」を取り上げる。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Roko
39
ホームスパンの布が出来上がるまでには、数多くの作業が必要です。まずは、羊の毛を刈り取り、洗ってゴミや汚れを除きます。羊毛の色そのままを使うこともあれば、染色をすることもあります。染色する場合は羊毛の常態で染色をします。羊毛は綿のような状態なので、それによりをかけ、太さをそろえながら糸にしていきます。 そうして出来上がった糸を使って機織りをします。色の組み合わせ、いくつもある織りの種類、糸の太さ、様々な布が出来上がっていきます。#ホームスパン #NetGalleyJP2024/03/01
まる子
20
イギリスから日本に伝わったホームスパン(HOME=家で、SPUN=紡ぐ)は、羊毛を 手染め 手紡ぎ 手織りしたウール。オーストラリア、ニュージーランド、イギリスからの輸入が多い中、畑の肥やしになっていた岩手県の羊の毛をアップサイクル。毛を刈り糸になるまで。そこからさらに機から反へなる工程がこんなに多いのか。ウール(温かい、燃えにくい、染まりやすい、汚れに強い、形崩れしにくい)はこれからの日本にも必要だと感じた。岩手県にはホームスパン作家、工房がまだあるので、これからの100年も伝え紡いでいく事を願って。2024/05/14
図書室のふくろう
3
羊から刈り取られた毛からゴミを取り除き、洗って毛並みを揃えるカードがけをして綺麗な綿のようになり、よりをかけられ細くて長い糸に紡がれていく過程は気の遠くなる作業。織り機で一枚の布にしていく作業もまたいくつもの工程を経て完成されていく。 [簡単に早く生産する世の中]に逆行するようなホームスパンの仕事を丁寧に紹介する本です。2024/03/20