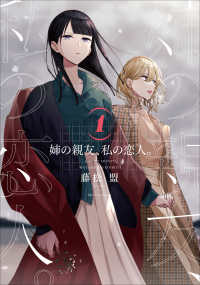内容説明
通常学級でのインクルーシブ教育は、具体的にどう実践すればいいのか。これまで数々の教育実践を世に問うてきた岩瀬実践をもとに考える。
目次
第1章 インクルーシブ発想とは
(つなぐ、つながることの弱さ;「集団の中の個」という考え方;関係性と合理的配慮 ほか)
第2章 インクルーシブ教育をどう実践すればいいのか
(対談)青山新吾×岩瀬直樹(4月の最初に「教室リフォームプロジェクト」を行う理由;「作家の時間」で子どもたちをみる、「PA」で人間関係を混ぜる;コンテンツだけ取り入れても意味がない ほか)
第3章 インクルーシブ教育の実践って?
(方法の前提になること(対談を経て);方法の目的化;子どもをどんな存在としてみるか ほか)
目次
第1章 インクルーシブ発想とは~岩瀬直樹実践が問いかけるもの~
第2章 インクルーシブ教育をどう実践すればいいのか(対談)青山新吾×岩瀬直樹
第3章 インクルーシブ教育の実践って?
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひさちゃん
6
インクルーシブ教育といえば、特別支援教育とすぐ思う自分が恥ずかしい。特別支援教育について書かれた本かと思ったが、内容はそれに特化するものではなく、子どもたち一人ひとりの違いを大切にした教育について書かれた本だった。「子どもを自分たちで伸びていく存在、学びのコントローラーを自分で操作する存在であるとみるところから出発すること」…何でも大人がやりすぎちゃうことは、子どもの「育つ」を阻害しているのかも、と思った。もう一度じっくり読もうと思う。2023/12/10
mori
5
一読していい本だなと思う。今までのぼんやりしたインクルーシブの他本とは一味違う。個別化と共同化。岩瀬実践の言語化し、通常の学級でのインクルーシブ教育を語っている。でも公立で実践するには覚悟がいるとも思う。2019/02/01
2h35min
3
イワセンの実践に学ぼうと思う。なかなか深かった。2019/08/07
BECCHI
3
今まで言語化されてこなかった岩瀬先生の実践がわかりやすく言語化されていました。大事にしなければならないことを何度も強調して伝えている。子ども観を磨くことや、コンテンツ重視に陥らないようにすべきことが大事と。でも、若い人を含めどうしてもコンテンツ重視になりがち。そこで、学校運営に関わる人たちが当たり前を見直す感覚を持って日々を過ごすことは重要だなぁと。それからどんな実践も完璧ではないということは肝に銘じたい。先生が楽しそうと思って実践を始めることは良いが、そこからは子供達と日々改善しながらやっていくことだ。2019/01/19
motoryou
2
そもそも、一人一人は違うわけだからどの場面であってもインクルシーブなスタンスと行動で支えられている状態が、目指していくことだな思う。そうなった時、その状態は教員だけで成立させられるものではなく、子どもたちを含めたその場のそれぞれが多様なつなりの中でバランスをとっていくものになるかな?と思う。それはヤジロベエ的なものではなく、自転車的なイメージを想像する。それぞれの「〜たい」という願いを、トライアンドエラーしながらみんなでこぐペダルが推進力。ハンドルは、リーダーの問いかけとエピソードの共有によって、かなぁ。2024/12/15
-

- 電子書籍
- 天尊、都市に再臨する【タテヨミ】第10…