内容説明
成層圏にダイヤモンドをまいて、太陽光を反射し地球を冷やす
――その結果、私たちは青空を失うことになるかもしれない
人間はこれまでに自然を思いのままにしようとした結果、環境を破壊してきた。
そして今、気候変動や生物多様性の危機を解決するため、
最新のテクノロジーを駆使し、さらなるコントロールを試みようとしている。
・川に電気を流し外来種のコイを操る「電気バリア」
・温暖化の海を耐え抜くサンゴをつくりだす「進化アシスト」
・毒を分泌するオオヒキガエルを無毒化する「遺伝子ドライブ」
・大気中のCO2を回収して石に変える「DAC装置」
・空にダイヤモンドをまいて地球を冷やす「ソーラー・ジオエンジニアリング」
こうした技術は自然を救う希望か、それとも絶望か?
『6度目の大絶滅』でピュリッツァー賞を受賞した作家による、待望の最新作。
全米各紙誌絶賛!!
ウェインライト賞 ライティング部門最終候補
ワシントン・ポスト紙 年間最優秀書籍10冊
タイム紙、エスクァイア誌、パブリッシャーズ・ウィークリー 年間最優秀書籍に選出
目次
【第1部】川を下って
第1章 シカゴ川とアジアン・カープ
第2章 ミシシッピ川と沈みゆく土地
【第2部】野生の世界へ
第3章 砂漠に生息する小さな魚
第4章 死にゆくサンゴ礁
第5章 CRISPRは人を神に変えたのか?
【第3部】空の上で
第6章 二酸化炭素を石に変える
第7章 ソーラー・ジオエンジニアリング
第8章 過去に例のない世界の、過去に例のない気候
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
37
気候変動や生物多様性の危機を解決するため、最新のテクノロジーを駆使するのは自然を救う希望か、それとも絶望か。具体的な事例を挙げて考察する一冊。川に電気を流し外来種のコイを操る電気バリアや温暖化の海を耐え抜くサンゴを作り出す進化アシスト、毒を分泌するオオヒキガエルを無毒化する遺伝子ドライブ、大気中のCO2を回収して石に変える装置、空にダイヤモンドをまいて地球を冷やすソーラージオエンジニアリングなど、どれも被害を食い止めようとしないと悪化する事例で、けれどどこまで手を入れるべきなのかはとても難しい問題ですね。2024/02/24
yyrn
23
人による大規模な自然の改変や遺伝子操作をする愚を取り上げ、人類はとんでもないことをしようとしていると警鐘を鳴らす本。改変が成功した事例が示されていないのは(利根川の付替えやトキの再導入等を想起しながら)フェアではないと思ったが、導入時点では成功だと思われたものが、その後予想もしていなかった災禍をもたらす事例が多数紹介されており、何をもって成功だと言えるのかと考えさせられた。しかし、地球温暖化対策として成層圏に大量の微粒子をまき散らし人工的に曇り空にしてしまおうという(火山の大噴火からの)アイデアとか、⇒2024/07/07
KUMYAM@ミステリーとSF推し
7
いろんな角度からさまざまな方法を検討するが、たしかにこういうやり方がビジネスとして成立するかが問題になるんだろう。どんなに良い事、必要なこととわかっていても、資本主義社会では儲からないとなるととたんに手を引く傾向があるから。2024/02/28
Go Extreme
2
再帰的論理 介入の悪循環 技術的コントロール 自然破壊と修復 逆説的解決策 シカゴ川の逆流 アジア鯉の拡大 予期しない結果 沿岸侵食 デビルズ・ホール・パピッシュ 保全依存的な種 管理なしに生き残れない サンゴ白化 援助進化 耐性種の育成 ケーン・トード問題 CRISPR遺伝子編集 炭素除去技術 化学風化の加速 カーボン・ネガティブ 火山噴火の人工複製 100万対1の効率 手つかずの自然の終焉 ハイブリッドな環境 人間が脊椎動物を上回る 「自然」の人工性 倫理的ジレンマ 気候制御の権力 良い人新世 謙虚2025/11/22
Kenzo Tada
1
世界の未来は破滅しかないのか。2025/06/25
-

- 電子書籍
- ソードアート・オンライン プログレッシ…
-
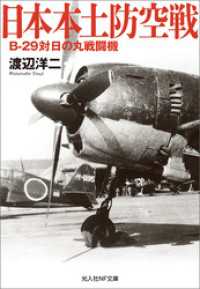
- 電子書籍
- 日本本土防空戦 B-29対日の丸戦闘機…
-
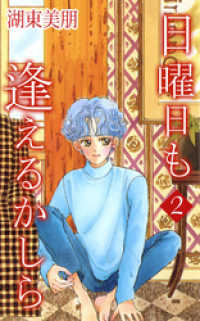
- 電子書籍
- 日曜日も逢えるかしら 2 コミックプリ…
-
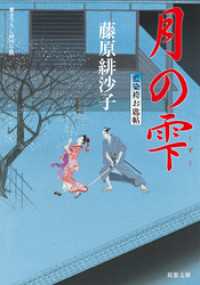
- 電子書籍
- 藍染袴お匙帖 : 8 月の雫 双葉文庫
-

- 和書
- 冬音




