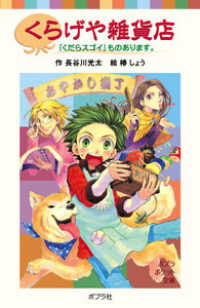内容説明
世界で最も多くの米兵が駐留し、米軍施設を抱える日本。米軍のみならず、終戦後一貫して外国軍の「国連軍」も駐留する。なぜ、いつから基地大国になったのか。米軍の裏の顔である国連軍とは。本書は日米の史料をふまえ、占領期から朝鮮戦争、安保改定、沖縄返還、冷戦後、現代の普天間移設問題まで、基地と日米関係の軌跡を追う。「日本は基地を提供し、米国は防衛する」という通説を覆し、特異な実態を解明。戦後史を描き直す。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
69
在日米軍基地の実態を明らかにする本ではなく、基地の「あり方」を論じた本。本書の最も重要な点は、日本にある主要な米軍基地のいくつかが国連軍の基地に指定されていて、別個に地位協定まで作られていることの指摘だろう。そしてその意味合いは極めて深く、現在・将来の基地の「あり方」に大きな影響を与えている。基地問題を論じるときにはこの問題を避けて通ることはできないことが理解できた。鳩山政権崩壊の一因が、彼が普天間基地が国連軍の基地という事実(つまり国外=アメリカには移転できない)を知らなかったからという仮説は興味深い。2024/02/19
風に吹かれて
23
戦後、1945年の米軍に続き、1946年に英連邦占領軍(BCOF)が日本上陸。順次撤退。1950年、最後に豪州が撤退を決定するが、撤退前に朝鮮戦争勃発、豪州は朝鮮戦争へ軍隊投入。国連安保理決議により加盟国に対し合衆国の司令部への兵力などの援助提供を勧告、東京に国連軍司令部設置、16カ国が参加。1951年、サンフランシスコ平和条約及び旧日米安保条約調印、1953年朝鮮戦争休戦、そして、国連軍を引き続きいつでも機能できるように関係国との国連軍地位協定の署名がおこなわれ1954年、国連軍地位協定発効……。 →2024/11/28
紙狸
16
2024年1月刊行。在日米軍基地の一部は、国連軍の後方基地でもある。起源は朝鮮戦争にある。米軍主体の国連軍が韓国を救った。米国と日本は、国連軍地位協定も結んで、国連軍加盟国も在日米軍基地を使えるようにした。実際、近年では英国軍やオーストラリア軍が、国連軍としての地位を利用して日本と安全保障分野での協力を深めている。この本が国連軍基地を広く紹介したのは意義がある。気になるのは、有事に米国が日本を守るのかどうかの議論が浅いこと。条約とその解釈を分析するだけでは一面的に過ぎる。同盟関係はもっと多面的だ。 2024/03/15
nagoyan
15
在日米軍基地基地という書名から想像されがちな所謂「基地問題」を扱ったものではない。僕らは、朝鮮国連軍の存在を歴史としては知っていても、米軍とは、異なった在り方で日本に駐留して居続けているとは想像もしないだろう。現在も日本にいることに認識がないか、さまなくば、在日米軍の別名に過ぎないと誤認しているかのいずれかではないか。本書は、国連軍地位協定の存在に注意を向ける。国連軍地位協定は、安保条約と日米地位協定とは別個に存在し、その特権は安保体制下の米軍を凌ぐ。2024/02/13
nishiyan
13
占領期から現代に至るまでの在日米軍基地の歴史を紐解きながら、米軍基地でありながら朝鮮戦争で結成された国連軍の基地でもあるという二つの側面を描いたことで、日本の安全保障の根幹を論じた新書。基地問題が解決しない理由は米国との関係だけではなく、国連軍基地であることにも言及した点は興味深い。日米地位協定に比べて認知度が低い、国連軍地位協定の存在だけでなく、問題点の多さには驚かされた。朝鮮有事や台湾有事の際には基地がどのような使われ方をするのか考えると肝が冷える。更なる在日国連軍の研究の進展が求まられるだろう。2024/07/04
-

- 電子書籍
- プロフェッショナル 仕事の流儀 長谷川…