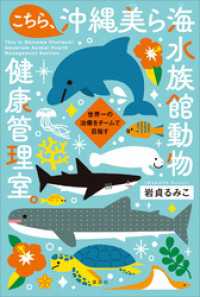内容説明
多くの犠牲者が出た治承(じしょう)・寿永(じゅえい)の内乱。武士は本当に戦死を一番の勲功と認識していたのか。戦功の認定基準や、討たれた首の取り扱い、大路渡(おおじわたし)をめぐる朝廷の葛藤、度々起こる生存説の流布などから、戦死への意識を解き明かす。鎌倉幕府による鎮魂や顕彰行為にも光をあて、勝者の役割と背後の政治性にも言及。敵も弔った武士の心性を読み解く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
takao
3
ふむ2024/05/07
onepei
3
「首」の章が興味深かった 総じて勝つと振り返る余裕が出る2023/11/19
剛田剛
2
•「鎮魂の論理」は政治権力の源泉が儀式にあることを想起すればそんなに難しいものではない。内乱が収束して秩序が回復されたなら、その秩序の頂点にある者が鎮魂の儀式を執り行うことは全く自然な義務であり、そこに政治的な意味を過剰に読み取る必要はない。•平家物語成立の「動機」に治承・寿永の乱に伴う死者の鎮魂と唱導があったことはすでに指摘されていることであるが、鎮魂は建墓や読経だけでなく、「死者のことを物語として語ること」によっても成されるものだったのであろう。2025/05/24
フランソワーズ
2
中世は宗教の時代と呼ばれるように、副題にある「生への執着、死者への祈り」は私たちには思いも及ばないものだった。「大路渡」や佐奈田義忠の討ち死に見られる生者の反応は、そこに為政者の思惑もあるとはいえ、とても興味深い事例だった。2024/05/04