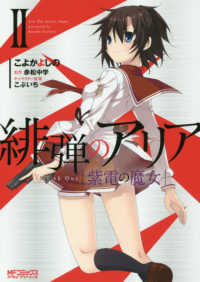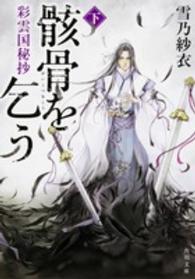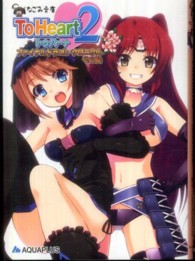内容説明
西郷隆盛の性格は、書状からみえる。豊臣秀頼の父親は本当に秀吉なのか。著者が原本を発見した龍馬の手紙の中身とは。司馬遼太郎と伝説の儒学者には奇縁があった――日本史にはたくさんの謎が潜んでいる。著者は全国各地で古文書を発見・解読し、真相へと分け入ってゆく。歴史の「本当の姿」は、古文書の中からしかみえてこない。小説や教科書ではわからない、日本史の面白さ、魅力がここにある!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きみたけ
243
著者は日本の歴史学者で国際日本文化研究センター教授の磯田道史先生。著書「武士の家計簿」が映画化された他、大河ドラマや歴史番組の時代考証、コメンテーターなどで活躍中。全国各地で古文書を解読し、歴史の本当の姿や日本史の面白さを伝える日本史好きにはたまらない一冊。古文書の内容が分かると、歴史的事項の裏付けや背景、当時の庶民の感覚など詳細な情報がダイレクトに伝わりとても面白いです。秀頼が生まれた日から逆算して、肥前名護屋で秀吉と淀殿が夜を共にしない限り実の子とならない、のくだりが興味深かったです。2022/01/27
パトラッシュ
220
本書の一部でもある磯田先生の新聞連載は毎週愛読している。古文書や史料から発掘した、まず歴史書には載らない瑣末な細部が何ともいえず面白いからだ。秀吉と本願寺の協力関係や築山殿の元の名前、毒見役の実情などは従来の歴史小説のテーマを逆転させる話だし、江戸時代に識字率がアップしたと知っていても出版文化がこれだけ発展していたとは気付かなかった。太平の世は書物の世であったからこそ庶民や女性にまで様々な知識が普及し、幕末維新の時期に列強の植民地にならずにすんだのは確かだ。本が失われた世界は人類消滅の時と確信してしまう。2020/06/18
AICHAN
198
図書館本。古文書を読むのが大好きな磯田道史さんのエッセイ風の著書。三方ヶ原の決戦で家康が逃げ延びることができたことに疑問を持つなんて、ただの歴史学者じゃない磯田さん。古文書を漁ってとうとうその謎を発見…。そのような面白い話がギュッと詰まっている。2020/02/04
れみ
194
様々な歴史上の出来事を古文書にかかれたことをもとに本。磯田さんのことはテレビではよくお見かけするけど本を読むのは初めて。古文書が本当に好きなんだなというのが伝わってくるし書かれた内容も読みやすくわかりやすい。ここ10年なるべく大河ドラマを見るようにしてたからか分かる話がいっぱいあって自分のなかに歴史の知識が増えてるのを感じられて嬉しかった。もしもう少しこの本を早く読んでたら、昨年浜松に行ったとき、同じ場所を訪れていても注目する場所が少し変わっていたかもと思う。なんか最近不思議と浜松に縁があるんだよね^^;2018/01/11
まさにい
191
やはり原典を読めるひとの話は面白い。かつて『ゆとり教育』というものが行われた。僕としては賛成であったが、世間は反対。理由は、円周を3.14ではなく3で計算するのか、というマスコミの無知な情報に踊らされてのこと。結局、詰め込み式の教育になっていく。詰め込み式の教育では、テストの点数がとれても、磯田さんのように、真に興味を追及する人材は育たない。最近の歴史小説がつまらなくなってきたのもそのせいかもしれない。博士論文にコピペが流行っているのもうなずける。この本を読み一歩深みに嵌る楽しさを教わったような気がする。2017/12/20
-

- 電子書籍
- 【単話】オルトナの月 第1話 角川コミ…