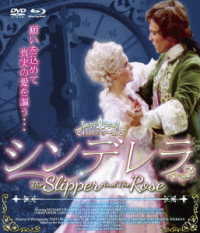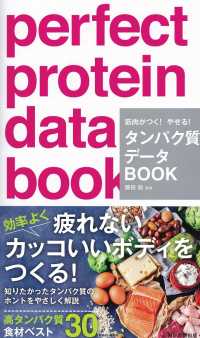内容説明
東京近郊の北武蔵野には、化学肥料に頼らない落ち葉堆肥農法が、新田開発以来360年後の今も継承されており、首都圏に供給する野菜の持続的な生産を支えている。この「武蔵野の落ち葉堆肥農法」が近くFAOの世界農業遺産に認定・登録される見込みであり、「土づくりを基礎とする世界でも稀有な農耕文化」として新たに評価されている。 「大都市近郊の奇跡」ともいえるこの農法の価値を土壌生態学の最新知見や江戸期の都市と周辺農村の物質循環、欧州の農業近代化の流れをふまえ、世界的な「土と堆肥の自然力」の低下との関係から考察する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たまきら
44
土を形成する化合物の説明がすごく単純明快でわかりやすく、図式を描きながら楽しみました。こういう説明、大好き!日本、特に東日本の土壌がもちろんメインですが、歴史的な「肥やし」史は大変興味深く、大名屋敷が一番上等だったとか、知らないことばかりで面白かったです。また、最後の章では健全な土壌を取り戻すために何ができるのか、を私が今まで持っていたものとは違う視点で提唱してあり、感銘を受けました。自然って、本当に何一つ無駄のない化学反応なんだなあ…。2023/11/18
みさどん
12
興味の高い所を中心に読んだ。中身がたっぷり。昔の有機栽培による野菜と、現代の野菜はその栄養素的な中身が違うだなんて、怖さも出てくる。土のことを考え出した良心的な農家さん方は化学肥料のみに頼らなくなってきているとは思うけれど、昔の農法に戻すことはできないだろうし、考えさせられることはいっぱい。うちでできたハクサイは虫だらけ。これを食べることができない現代人も多いはず。せめて我が家は化学肥料は少なめに野菜作りをしたい。ぬかやもみがらや炭や魚粉を使う。でも、そのぬかだって欠乏ぬかなのだろうな。2024/01/09
セヱマ
7
珍しい、地理学者が書いた農業の本。 やや近代農業批判が強い気がするが、結構面白い。 埼玉三富地域の、平地林を活かした短冊型畑地の落ち葉堆肥方法が、2023年にFAOの世界農業遺産に登録された。筆者はそれに尽力された人である。土と農と食のワン・ヘルスを取り戻せ、が主論と感じた。江戸の下肥に、西洋の栄養説に、米国のダスト・ボウルに、緑の革命に、農業史への展開もあり、農業史好きには嬉しい。2024/02/09
kamekichi29
4
日本とヨーロッパの農耕文化史。化学肥料のメリットも伝えながら、長らく大量に使うことによる弊害と持続可能な農業への転換を、東京近郊の北武蔵野で昔から行われている落ち葉堆肥嚢胞を例に挙げながら提言。2024/03/27
Humbaba
2
農業は人が生きていくうえで欠かすことのできないものである。必要とされる生産量は人口の増加と共に増え続けており、その傾向は今後も続いていくことが予想される。一方で需要を満たすほどに生産が増えているかというとなかなか難しいところがあり、まして将来にわたって増え続ける可能性は高くない。これまでのやり方では一時的には増加してもそれが土地を瘦せさせてしまうことになりかねない。自然は循環するものであり、それに合わせて行くことこそが将来にわたっても高い生産性を保つためには必要となってくる。2025/04/27