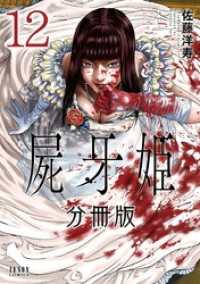内容説明
第一次大戦後,資本主義の急激な高度化・都市化の進展によって引き起こされた社会変容は,日本の知識人に激しい衝撃を与え,20年代以降,文化的本来性をめぐる言説を大量に生み出した.西欧でも同時期に出現したこのあまりにも近代的な現象=「近代の超克」を新しい光のもとに捉え,日本の近代思想史像を一変した,衝撃の書.(全2冊完結)
目次
凡例
第四章 文化的記憶の持続
日常性という恐慌
文化的存在論──日常性の避けられない原初性
偶然の必要性
文化の二重性格──日常生活の重層性
国民性格の文化化
人間関係を家化する
第五章 共同 体
共同 体の記憶術
民衆を形象化する
芸術、アウラ、繰り返し
第六章 歴史的現実
実存、経験、現在
「生活文化」
「技術の力」
民族主義とファシズムという亡霊
注
『近代による超克』の切断(梅森直之)
ハリー・ハルトゥーニアン著作目録
ハリー・ハルトゥーニアン著作邦訳目録
用語リスト
(上巻目次)
日本語版への序文
序 すべては歴史の名の下に
謝辞
第一章 モダンライフという幻想
第二章 近代を超克する
多様な出来事の継起の終わりとしての事件
アメリカニズム
表象の問題と歴史の地位
第三章 現在を知覚する
「モダンライフ」という約束
「機械というプリズム」を通して
「群集の人」──大衆文化のアクチュアリティ
日常生活の哲学化
歴史編成と民衆娯楽
街、隠れ家、主体性
注
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ポン
3
モダニズム批判が構造ではなく表象の批判に留まったことに、民俗学、国文学、考現学、史学等日本の諸学問の限界をとらえる。しかも、(だからこそ)その批判は結果的に近代的支配の言説に包摂されてしまう、という論。外国の方の日本研究はこの手の語り口が多い。なぜ、日本の先学者達が表象の批判を重要視せざるを得なかったのか、という問い(つまりそれ以前に遡った近代日本のエートスの探究)のほうが本質的に重要だと思うが、どうだろうか。とはいえ、近代諸思想を考える上で、欠かせない名著か。戦後史学も見据えた批判として読み取った。2013/12/31



![Uno, molti, tutti : Gv 17,21 e la sua ricezione nella letteratura cristiana antica (Testi, ricerche e fonti [nuova serie], 71) 〈[nuova serie], 71〉](../images/goods/../parts/goods-list/no-phooto.jpg)