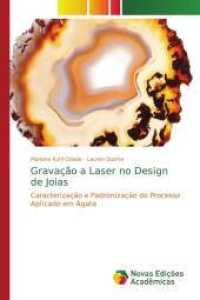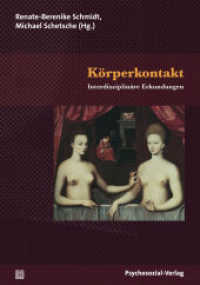内容説明
効率性や日々のSNS通知に追われ続ける現代人にできる最大の抵抗は「何もしない」ことだ。自らの思考と創造性を取り戻す術とは
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アナクマ
23
序章_それは「注意経済から身を引くことであり、その後何か別のもの(時間と空間)とのかかわりを持つこと」。黒板五郎の〈知らん権利〉を、その年に生まれた反資本主義なアメリカ人が再構築した一冊。「維持よりも破壊のほうが生産的だというロジック」への問題意識と認識については、詳しく確認してみよう。◉ややこしい世界観を感じる要因は「どっちつかずの状態に身を置くのは悪いことではない」という著者の生活環境の先鋭さ? こちらの盆暗さ? 翻訳のせい?。お釈迦様の手のひらを彷徨うようなエッセイ(つまり〈試みを続けること〉)→2024/04/28
アナクマ
21
3章前半_甕住まいのディオゲネス、森の隠者ソロー、「わが国でもっとも有名な拒絶」者バートルビーなどを例に。◉「世に普及する法や習慣」に囲われた第一の空間。それを拒絶し個人の自制力と法により「高みから見下ろす」第二の空間(たぶん)。その次に現れる「第三の空間」は、人びとがたがいに連携して集団的拒絶を行う「不服従のスペクタクル」。「上手くいけば…柔軟な合意構造をとる二次レベルの自制と鍛錬が成立する」という。◉あくまでも個人から発した〈拒絶〉の連携が上手くいくためには何が必要なのだろうか。→2024/11/01
きゃれら
20
都心の無人書店のワゴンにおいてあってタイトル・表紙デザインからしても軽めの自己啓発本と思いきや、硬派・重厚な思想書と言っていいエッセイだ。起きている間スマホに触らずにいられない我々の「注意」がマネタイズされ続ける異常な状況への抵抗を呼び掛けている。引用される作家は、エピクロス、スキナー、アレント、荘子、フーリエ、ル・グィン、ディオゲネス、ドゥルーズ、メルヴィル…。この中で特にアレント「人間の条件」とメルヴィル「代書人バートルビー」は本書の極めて重要な軸となっている。難しい議論だが一読の価値はある。2024/03/28
アナクマ
16
3章_3度目の挑戦も敗退。よくわかりませんでした。わずかに理解したのは、面白哲人ディオゲネスも森の賢人ソローも、余白の中に身を置けたのは「有利な状況によるところが大きかった」という周辺事情(反骨の事務員バートルビーは「監獄で息絶えた」)。あと、何かを主張するときには相手の反応をよく確かめながら、相手の理解の範疇を飛び越えすぎない言葉づかいと論理を用いなさい、という戒めでした。面白そうな本なんだけどね、煙に巻かれまくり。今後はみなさんの投稿を頼りにします。2025/09/14
双海(ふたみ)
10
SNSなど、人々の関心を売買する「アテンションエコノミー(注意経済)」が跋扈する現代。そこから抜け出すために必要なのは、効率主義から離れてみること――つまり、「何もしない」ことが大切だと説く。つながりを避けては生きられない時代に自らにふさわしいあり方を見つけ出すヒントを、哲学者、鳥たち、該当を行き交う人びとが教えてくれる。2025/03/16