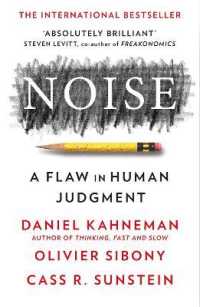内容説明
「日本語の歴史」シリーズ第2弾。現代において辞書は買って使うものだが、江戸時代以前は写すことで所持し、自分で作り上げるものだった。辞書の「作り手」「使い手」の姿を通して、各時代の日本語を活写する。
目次
はじめに──辞書が語ること/辞書というのぞきめがね/辞書の作り手、辞書の使い手/辞書を写す/辞書が語ること/第一章 辞書の「作り手」と「使い手」──平安~鎌倉時代の辞書/最初の辞書/1 百科事典的な『和名類聚抄』/歌人がつくった辞書/内親王の読書のための辞書/意義による分類/外界を分類する/風月と世俗と/動物園があったら/2 漢文訓読がうんだ『類聚名義抄』/音義書から辞書へ/観智院本/辞書の写し手/多くの和訓/こんな和訓もあります──ツイクフ/こんな和訓もあります──コロロク/異字同訓/第二章 辞書を写す──文学にも日常生活にも対応する室町時代の辞書/和語も見出し項目となり始める/1 成長する辞書『下学集』/初学者向けの辞書?/語釈がない見出し項目/違いがわかりますか?/2 文学とも関わりが深い『節用集』/三条西実隆と『節用集』/戦国武将と『節用集』/飛鳥井雅親と『節用集』/和語もふんだんにとりいれた辞書/和歌や連歌とのかかわり/自分でつくる辞書/和語と漢語との重なり合い/第三章 日本語の時間軸を意識する──江戸時代の三大辞書/一〇世紀の書きことばを一八世紀の話しことばに/書きことばと話しことばとの関係/遠めがねで『古今和歌集』をみると/『古今集遠鏡』の口語訳/1 「今、ここ」のことばを集めた『俚言集覧』/みんなで作った辞書/「俚言」とは?/2 古典を読むための『雅言集覧』/狂歌師がつくった辞書/古語の用例集/「雅言」とは?/3 現代の国語辞書の先駆者『和訓栞』/現代の国語辞書のさきがけ/見出し項目のひろがり/こんな見出し項目があります──さっぱりさわやか/あて字・おどり字・湯桶読み/第四章 西洋との接触が辞書にもたらしたこと──明治期の辞書/英語日本語対訳辞書/1 ヘボン式ローマ字綴りのもととなった『和英語林集成』/ヘボンについて/見出し項目がローマ字で書かれている辞書/ローマ字の綴り方/見出し項目にあてる漢字列/『和英語林集成』が見出し項目とした語/2 いろは順の横組み辞書『[漢英対照]いろは辞典』/高橋五郎について/西洋字書と肩を並べる日本の辞書/『[漢英対照]いろは辞典』が見出し項目とする語/3 五十音順配列の辞書『言海』/大槻文彦について/普通語の辞書/『言海』をめぐる人々/五つの大事なこと/『言海』が見出し項目とした語──古語・訛語/堂々巡り/おわりに──辞書が教えてくれたこと
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
ヤギ郎
kuchen
-
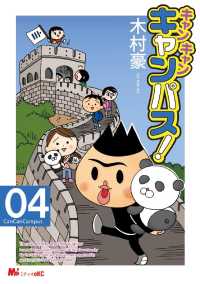
- 電子書籍
- キャン・キャン・キャンパス!(4)