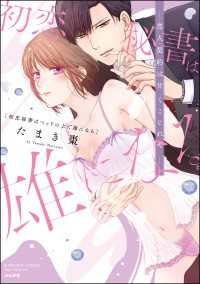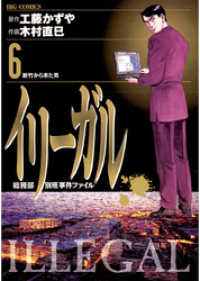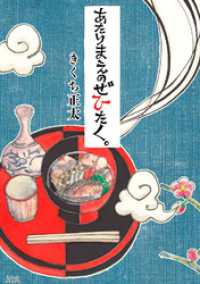- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
よく知られるように平城京・平安京以外にも、古代には数多くの宮都があった。王権の所在地であり国家統治の中枢だった王宮は、やがて「百官の府」と称され、京域に貴族官人や庶民が集住し都市文化が萌芽。それは遷都と造都を繰り返す中でもたらされた。半世紀以上にわたり、古代の宮都を訪ね歩いてきた著者が、過去の景観と現在を比較し、文献史料を再検討することによって、宮都の知られざる事実を掘り起こす。通説にとらわれずに史実を明らかにしてきた碩学による宮都案内。
目次
序章 峠の文明開化/峠に心惹かれて/文明開化の始まりとともに/竹内街道──世界に開かれた大道/第一章 宮都の原郷/1 近親結婚の思惑──皇祖母尊の時代/純血主義の弊害と「吉野の盟約」/ゴッドマザーとしての斉明女帝/愛情深き女帝の最期/2 飛鳥の「田身嶺」/女帝を大規模工事へと駆り立てた「豪気」/「田身嶺」とは何か/国家的饗応・饗宴施設としての嶺/3 真神原の宮処/「入鹿の首塚」が語りかけるもの/国際都市としての飛鳥真神原/第二章 遷都の条件/1 遷都の予兆/遷都に伴うネズミの異常行動/難波への遷都、中大兄皇子による人心操作?/近江への遷都、そして「予兆」という政治手法の終焉/2 難波長柄豊碕宮と難波宮/孝徳天皇による新宮造営/孝徳天皇と中大兄皇子の対立/前期・後期難波宮をめぐって/3 近江大津宮/遷都実現までの対外的な施策/首都防衛ゾーンとしての近江国/消えた大津宮を探し求めて/因縁の対立の果てに/壬申の乱と倭京/第三章 藤原京へ/1 新京の構想/御薪の宴、そして「みやこ」のあり方の変容/天武天皇の遷都への躊躇/最晩年に至っての造都造営への意識の高まり/2 「新益」藤原京/持統天皇に受け継がれた造都事業/道路の造成から始まった「都づくり」/藤原宮と藤原氏の関連性/3 藤原京という時代/飛鳥京と藤原京の非分離性/〝一卵性家族〟の八角墓──飛鳥時代の終焉/第四章 平城京へ/1 百官の府/母・元明女帝に引き継がれた遷都構想/貴族官人の母胎としての「百官の府」/「宮城図」の詳細/「倭京」の到達点としての平城京/2 羅城門はあったか/史料から見えてくる羅城門/歓迎行事の推移とともに/羅城がないのに羅城門?/3 「不改常典」の謎/元明の詔の特異性/歴代天皇即位の詔における「不改常典」/首皇子の出生から生まれた「不改常典」/持統天皇の最晩年における執念の所産として/第五章 流離する宮都/1 平城京・恭仁京/波乱含みの聖武の治世/藤原広嗣の乱を受けて/〝遷都ならぬ遷都〟からの恭仁宮造営/短命であった恭仁宮の全貌/2 紫香楽宮・難波宮/聖武天皇の紫香楽宮行幸と「大仏建立の詔」/四度目の行幸における重大な決断/橘諸兄による難波宮への着目と「皇都」宣言/〝彷徨五年〟の果てに/3 北京(保良宮)・西京(由義宮)/「北京」近江保良宮の成り立ち/藤原仲麻呂による新羅出兵計画/異変、そして廃墟と化す/「西京」河内由義宮の成り立ちと道鏡の野望/宣託事件の経緯/逆効果に終わった法均・清麻呂姉弟の策略/称徳女帝の孤独を癒やした由義宮行幸/第六章 「山背」宮都へ/1 皇統の転換/「倭京」から「大和宮都」、そして新たな宮都へ/皇太子をめぐる変化/光仁天皇の施策と天皇呪詛事件/存在感を増す藤原式家/2 遷都の思想/桓武天皇の即位と氷上川継の乱/事件をめぐる様々な思惑/桓武天皇に芽生えた強い自覚と個性的な施策/詔・勅から垣間見られる天皇の思い/蝦蟇の大群の大移動、そして遷都のスタート/3 遷都と棄都の間/桓武天皇による長岡遷都/遷都以後の動き/長岡造都事業の本格化と種継暗殺事件/種継の死による大きな打撃/桓武天皇に萌した長岡棄都の思い/長岡遷都の歴史的位置づけ/第七章 平安新京/1 京中巡幸/桓武天皇を襲った度重なる不幸と平安遷都構想/熱心な「京中巡幸」といくつかのエピソード/効率的に進められた造都事業/存在感を失う「大和国」と新都の活況/新京誕生を寿ぐ踏歌/2 軍事と造作/桓武天皇による蝦夷対策/征夷大将軍・坂上田村麻呂の深い歎き/田村麻呂・アテルイの伝説化、そして歴史的和解/3 徳政相論/病に伏して/諸負担軽減策の総決算としての「徳政相論」/死を目前にしての早良親王への謝罪/見事なまでの「終活」を遂げて/第八章 王朝文華の源泉/1 平安定都/平城天皇の失意と「二所朝廷」/嵯峨天皇の配慮と薬子の変までの経緯/仲成・薬子兄妹の孤立と平城天皇のその後/2 王朝の宮廷/平安京遷都による変化──葛野川への度重なる行幸/伊勢斎王の禊についての変化──葛野川から賀茂川へ/文化的起爆剤としての平安京遷都/3 清涼殿と後院/平城天皇の早とちり/平安初期の天皇と清涼殿・仁寿殿の関わり/天皇とキサキ──後宮の拡大/過去の教訓から造られた「後院」/第九章 平安京三題/1 鴨川辛橋/平安京の人々と河川/『将門記』に見る外港設営の重要性/平城京への「望郷の念」の象徴として/鴨川辛橋にまつわる人々の物語/2 諸司厨町/飛 匠の活躍──奈良盆地における国名村の存在/舎人たちの問題と宿所/記録に見る諸司厨町/国名村から諸司厨町へ/3 遣唐船始末/文化事業としての遣唐船派遣──最澄と空海/遣唐使派遣後の日唐関係と『竹取物語』/道真による遣唐使派遣中止とその後の誤解/終章 京都が「京都」でなくなる時/1 大内裏の歴史を辿る/究極の「みやこ」としての平安京/大内裏図から見えてくるもの/大内と里内/貴族の存在形態の変化とともに/2 京都御所/内野/存在感を増す武家と閑院内裏/「関東の沙汰」の歴史的意義/3 羅城門の復元に向けて──平安京の過去と未来をつなぐ/梅小路公園の歴史的意味/「八条の泉」をめぐって──忠盛と西行、そして清盛/八条水閣についての新たな理解/『続日本紀』『日本後紀』に見る桓武天皇の行幸/羅城門がもつ現代的・今日的な意味/おわりに/基本史料/宮都関係略年表
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
眉毛ごもら
onepei
おおい