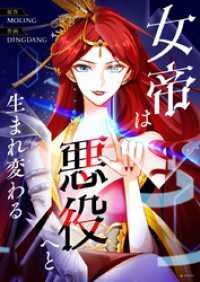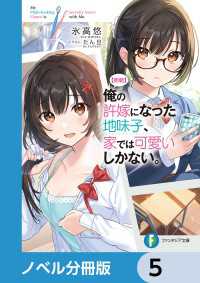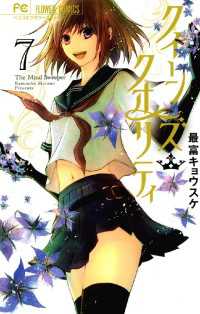内容説明
暗闇が消えると何が失われるのか?
生物学者が詩的に綴る、感動の科学エッセイ。
2022年度 英ウォーターストーンズ ポピュラーサイエンス部門
ベスト・ブック獲得
スウェーデンから、アメリカ、ドイツほか各国で続々翻訳
闇がなければ光はなかった 闇は光の母 ――谷川俊太郎
いま、街灯の照明をはじめとする人工の光が、多くの夜の自然の光を奪っている。その結果、古来から続く生物の概日リズム(体内時計)を乱し、真夜中に鳥を歌わせ、卵から孵化したウミガメを間違った方向へ誘導し、月明かりの下の岩礁でおこなわれるサンゴの交配の儀式すら阻害している。
本書は、人工の光による自然への影響(=光害:ひかりがい) をひもとき、失われた闇を取り戻そうとする呼びかけである。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kuukazoo
18
加齢のせいか最近車のヘッドライトがめっちゃ眩しくてこんな強い光をまともに受けてたらヤバいとLEDの害を感じずにいられないので読んでみた。著者はスウェーデンのコウモリ研究者。過剰な人工光により昆虫、鳥類、夜行性動物、植物の生体リズムが崩れ、生態系が危機に瀕しているなど「光害」の深刻さを説く。もはや暗闇や夜も守るべき自然環境であり、ダークツーリズムに見られるように地球の「絶景」の1つでもある。確かに明るさは文明の象徴であり安全をくれるものであるが過剰な人工光は人間の健康にもよくない。夜更かしはやめよう...2024/01/09
DEE
6
スウェーデンのコウモリ研究者である著者が、明るすぎる現代に警鐘を鳴らす。強すぎる光で集まる昆虫の生態系が崩れ、それを捕食する動物たちにも影響を及ぼす光害。夜に受粉する蛾や、蚊などを捕食するコウモリ、そういった小さなものが巡り巡って人間にも確実に害を及ぼしていく。今の夜は確かに明るすぎるし、余計な照明や電飾が多すぎる。キャンプしてて思うけど、暗闇ってときには心地いいものなんだけどね。2024/01/26
W
3
少しくらい暗闇に思いを馳せて暮らしてみようかと思った本。キャンプ場のトイレに群がる蛾を敬遠するのではなく、誰がその蛾の生活リズムを乱しているのかを考える。夜間勤務に就く人は、昼間勤務に就く人と比べて一部のガンの罹患率が高いという恐ろしい話も。眠りにつく体制に入る時、段々と食欲が抑制されていくのは、はるか昔に真夜中、暗闇の中食料を狩りにいけない人類が育んだ習性から来ているというのが面白かった。2024/12/18
K
3
読書会で勧められて読んでみた。自販機にタムロする虫が少なくなった気はしてたけど街が明るくなりすぎたせいだったのか。密室なら暗闇は作れるけど外で暗い場所って少なくなったよな…。暗い場所を探してみよう。2024/12/05
hahaha
2
新聞の書評で紹介していたので読んでみた。光害(ひかりがい)について、人間・コウモリ・昆虫・鳥・魚などへの影響を様々な事例を基に紹介した本。暗闇を追い払うための過剰な人口の光が自然界に悪影響を及ぼしている。夜や暗闇は人間にとっては不便かもしれないけども、自然界ではその暗闇の中で多様な営みがあり、それが巡り巡って人間に影響を与えている。沈黙や闇、静かな時間はもはや贅沢な時間なのかもしれない。スマホを置き、電気を消し、静かに夜空を見上げたり、ボーっとしたり考えたりすることはとても豊かな体験に違いない。2025/03/30