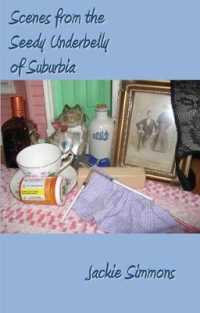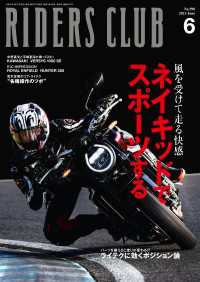内容説明
一次史料にもとづく堅実な分析と考察から、幕藩官僚=「職」の創出過程とその実態・特質を解明。幕藩官僚制の内実を、明瞭かつコンパクトに論じた日本近世史の快著。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
122
日本の政治は朝廷や幕府を問わず、関白や将軍、執権らの意向に従う人治統治が続いてきた。いわば「天下人」の意向が最優先で、その失敗や歪みへの不満が一揆や戦争の原因となった。江戸時代も三代家光までは同様の形で来たが、家光の病を機に将軍不在でも政治が滞らぬよう法や制度を支える官僚組織が整備されていく。多彩な役職を経験させて人材を育成し、基本は身分制ながら昇進昇給できるシステムは現在の官僚制の原型といえる。旗本や御家人から実力で大名クラスへ家格を上昇させていく姿は、身分による閉鎖的な権力独占のイメージを一新させる。2023/12/17
うえぽん
33
日本近世史の専門家による幕藩官僚制に係る一般向け著作。江戸と明治、戦前と戦後の間は、通常は断絶要素の方が強調されるが、継続要素も実は重要。例えば、福沢諭吉を含め、一般的に幕藩官僚制における昇進は、家格や身分に縛られ、極めて閉鎖的なものと捉えられている。この本は、一次資料を丹念に調べた結果、限定的とはいえかなりの昇進制が存在し、それによる領知・知行高の増加と相続によるその継承が財政負担増に繋がり、対応策を必要としたことを明らかにしており、明治期以降との異同について、より丁寧な議論が必要であることが理解可能。2023/12/03
MUNEKAZ
14
江戸幕府の人材登用制度をまとめた一冊。最初に大久保長安と大岡忠相を比較することで、天下人に抜擢された出頭人が何でも屋で仕事をこなす「人」によった幕府創成期から、昇進ルートに乗って与えられた「職」に専心する制度に変化したことがよくわかる。後半は『寛政諸家譜』を分析することで、巷間で言われるような江戸幕府の人事制度に対する閉鎖性の指摘に反論を試みている。労作だとは思うが、結局は親の身分や出自に縛られているので、これだけでは決定打にはならないかなと思ったり。2024/12/04
浅香山三郎
11
江戸時代の幕府の官僚制について、膨大な史料をベースにして概説する。大久保長安や大岡忠相といふ、一般にもある程度知られた人物を素材にその履歴を明らかにし(Ⅰ章)、出頭人の能力に即して職が与へられる段階と、官僚制の定着のなかで有能な人物が階梯を踏んでいくありやうへの、制度的変遷を示す(Ⅱ章以下)。1頁ごとの情報量が充実し、その背後には膨大な一次史料による情報の蓄積が窺はれる労作。2024/02/26
wuhujiang
3
本書第一章で出頭人の代表として大久保長安を、幕府管理機構が整備された後の政治家として大岡忠相を挙げる。有能とされる両者の仕事ぶりを比較することで、江戸初期と以降で幕府の「職」が整備されたんだよということが自然と飲み込めるのは素晴らしい構成だ。本書の説明に"武家社会を「身分や家格に縛られた閉鎖的な社会に再考を迫る」"とあるが、本書の内容を表すのにやや不適切。昇進にも結局出自や家格による限界はある。ただし、ガチガチに縛られているわけではなく本人の能力や努力で昇進する余地はあったよということ。2023/10/24