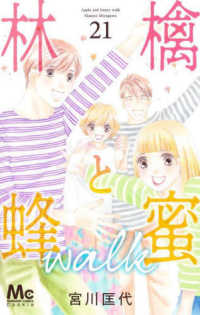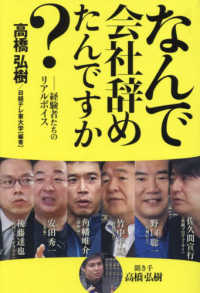内容説明
NHK「ブラタモリ」の放送を契機として、地質や地形が幅広い層に注目されています。本書は「都道府県の『トリセツ』」でも紹介した日本各地の地学のテーマを、より有機的につなげて「日本列島の誕生と今見えている地形の魅力」が時系列に理解できる一冊です。冒頭では簡潔に地球誕生のヒストリーを紹介。次に、日本列島誕生を理解するうえで必要なプレートテクトニクス(プレート理論。地球の表面上に何層かに重なるプレートが地球上のさまざまな地学現象を説明するという考え方)を図表等を用いながら分かりやすく解説しつつ、大陸から離れて島弧(日本列島)をなすまでを紹介。終章では、日本各地に分布する必見ジオサイトを地図や写真を添え、その成因などに迫ります。
※一部コンテンツが収録されていない場合があります。
-
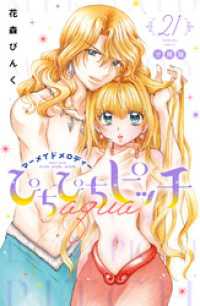
- 電子書籍
- ぴちぴちピッチ aqua 分冊版(21)
-
![ヤングマガジン サード2017年 Vol.2 [2017年1月6日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0383717.jpg)
- 電子書籍
- ヤングマガジン サード2017年 Vo…