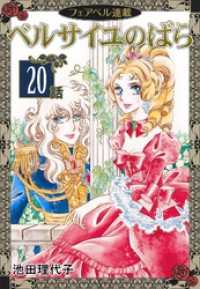- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
2022年、文章生成AI「ChatGPT」や画像生成AI「Stable Diffusion」など、一般ユーザーも気軽に使える生成AIサービスが次々と現れて世界に衝撃を与えた。すでに「一億総AI活用時代」が到来した様相だ。「人間の仕事が奪われる」などとメディアは煽るが、その特性を正しく知って使えば、生活やビジネスの効率が大幅に上がるのは確実である。本書は最新のAI研究からその歴史、仕事への活かし方、AI時代に人間が鍛えるべき能力まで、人工知能研究の第一人者が解説。「AIを使う人間」と「AIに使われる人間」の分かれ目がここにある!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
117
ディープラーニングの歴史、生成AIの活用法・リスクなどがとても分かりやすく解説されており、この分野に疎い私には大変有難い一冊であった。それでも、生成AIに対する懐疑を拭えないでいる私にとって衝撃的だったのは、本書が、GPT-4と著者との共同執筆だという事実。その結果、一冊の本を書くのに最短でも24時間かかるのに、本書は、10時間で第一稿が完成したと言う。使うべきか否かというゼロ百の議論ではなく、「生成系AIは、私たちが行う思考のプロセスを補完するツール」として上手く活用していくことが必要なのかもしれない。2023/08/15
おせきはん
35
生成AIの活用方法に関する具体的な紹介が参考になりました。これまでも英文和訳には何度か使ってきましたが、情報を整理したり、ある事柄の概要を把握する際などにも、もっと積極的に使ってみます。2024/02/17
kan
27
AIネイティブの時代、AIを使いこなす人間であれというのは全くその通りだと思う。教育現場でそういった人材を育てるために必要な、生成AIの基本的事実と、それを応用するヒントがいくつもあった。本書はAIによる下書きを利用したそうだが、勤務校の生徒もChatGPT等を用いたとわかる作文やレポートを提出してくることがある。生徒に身につけてもらいたい力を再度考え、課題の与え方や授業を見直したいが、著者の言うホスピタリティを英語教育で育むには、「定型処理」の訓練を経た言語運用能力が必須なのでなかなかイメージできない。2024/03/31
ホシ
27
ChatGPTを主として生成AIの概要・活用法・原理・歴史・リスク・展望について示されます。原理と歴史はチンプンカンプン。得られた学びは「AIは思想を映す鏡」であるという点。以前、生成AIを助手や秘書に喩える記事を見ましたが、しっくり来なかったのです。AIって助手や秘書と違って意思がないからね。著者は人が鏡の中に別世界があると錯覚するように、〈AIが理解する〉も錯覚に過ぎないという事を理解する必要があると主張します。これ、物凄く重要なんじゃないかと思う。2024/02/08
サト
23
これからの時代に意識することは、錯覚と、真心と思いやりです。▪️錯覚。この世界は錯覚があるから今があります。理論の話も書かれてますが、錯覚という表現は哲学的。▪️真心と思いやり。生成AIの時代で必要になる能力のこと。今は価値がないことでも、他の全てをAIに代替された後に残る人間性。分かる気がします。▪️『「価値ある能力」は時代によって変化する』節について。まるで『サピエンス全史』総括のような内容を、著者の専門分野から切り込んでいて興味深く読めました。(全編の中から面白かった一部をコメント欄へ)2025/11/18