内容説明
黒人であることで警官から疑われる場合のように、聞き手の偏見のせいで話し手が過度に低い信用性しか受け取れない「証言的不正義」。セクハラの概念が存在しない時代にそれに苦しんだ人のように、集団的な解釈資源のせいで経験の理解を妨げられ不利な立場とされる「解釈的不正義」。認識論・倫理学・フェミニズム哲学を横断する思索。
目次
日本語版への序文
序 文
序 章
第1章 証言的不正義
1・1 権力
1・2 アイデンティティの力
1・3 証言的不正義の中心事例
第2章 信用性の調整における偏見
2・1 ステレオタイプと偏見的ステレオタイプ
2・2 偏見なしの証言的不正義?
2・3 証言的不正義の不正
第3章 証言の徳認識論的説明に向けて
3・1 推論主義と非推論主義の論争から新たな立場をスケッチする
3・2 責任ある聞き手とは?
3・3 有徳な知覚──道徳と認識
3・4 感受性を訓練する
第4章 証言的正義の徳
4・1 偏見を修正する
4・2 歴史、非難、そして道徳的落胆
第5章 証言的正義の系譜学
5・1 真理についての第三の基本徳
5・2 認識と倫理のハイブリッドな徳
第6章 原初的な意義──不正についての再検討
6・1 二種類の沈黙
6・2 知識の主体という考えそのものについて
第7章 解釈的不正義
7・1 解釈的不正義の中心事例
7・2 解釈的周縁化
7・3 解釈的不正義の不正
7・4 解釈的正義の徳
結 論
原 注
訳 注
監訳者解説[佐藤邦政]
訳者あとがき[佐藤邦政・飯塚理恵]
文献一覧
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
11
哲学も倫理学も自分自身の(公のものについても他者や社会のものについても語りますね)正しさや正義については雄弁に語り、自らの内側のそれらについて見つめ続けるけれど、不正義については正義の反対にある概念として程度のぼんやりさでしか語らない。読者にそれを気づかせながら、認識的不正義と解釈的不正義について説明し、不正義の成り立ちについて語る。うっすらと抱いていた認識的正義と解釈的正義に対する鬱陶しさと嫌悪感みたいなのが何に由来するのかもぼんやりと見えた気がする。再読したい良書でした。2023/08/10
Akiro OUED
4
正義が哲学や倫理学のテーマになるのなら、不正義もテーマになるはず、という視点が面白い。反面教師という言葉もある。ステレオタイプが証言的不正義を生み出し、社会的経験の欠如が解釈的不正義を生み出す。最近は、LGBTQ+を押し出した解釈的正義が攻勢に出てるけど、やや鬱陶しい。好著。2023/05/28
Go Extreme
2
哲学は正義については雄弁、不正義に対してほとんど何も語らない 認識的不正義:社会的アイデンティティに対するステレオタイプ→知識の主体としての能力を貶められる不正 証言的不正義:偏見的ステレオタイプ→不当に低く見積もる→能力を貶められる 偏見的ステレオタイプ=潜在的バイアス 証言的感受性という徳:偏見的ステレオタイプを自覚→信頼性の高い仕方で中和、知的徳&倫理的徳 認識的な自然状態:情報の獲得・シェアし蓄える・信頼関係安定化 解釈的不正義:解釈的周縁化→集団的な解釈資源不足→自分の経験を理解・意味付けできず2023/05/08
tkg
0
不正義を非難できるのかについての議論が特に興味深かった。また、訳文が読みやすいのが有り難かった。2024/12/13
kuro
0
解釈的不正義、解釈的正義の徳を個人に帰せない(行為者がいるとする議論も今ではあるようだけど)という発想が刺激的だった。徳は個人主義的な問題にされがちだけれど、徳を社会の問題にする切り口として面白いのではないかと思った。2024/06/19
-

- 電子書籍
- あなたがしてくれなくても 分冊版 10…
-

- 電子書籍
- うちのタニシ【タテヨミ】第32話 pi…
-
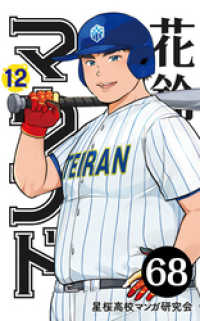
- 電子書籍
- 【分冊版】花鈴のマウンド 12巻(2)
-
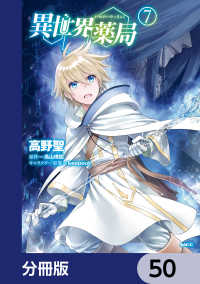
- 電子書籍
- 異世界薬局【分冊版】 50 MFC
-

- 電子書籍
- 見つける東京




