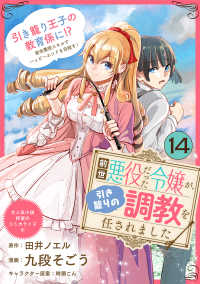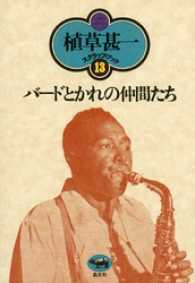- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
腐敗し白骨化してゆく亡骸の変化を、九つの段階で描く九相図。仏教とともに伝来し、日本に深く根を下ろしたこの不浄の絵画は、無常なる生命への畏れ、諦念、執着を照らし出す。精気みなぎる鎌倉絵巻から、土佐派や狩野派による新展開、漢詩や和歌との融合、絵解きと版本による大衆化、そして河鍋暁斎や現代画家たちによる継承と創造へ――。芸術選奨新人賞・角川財団学芸賞ダブル受賞作に補遺を付し、全作品をカラー掲載する決定版。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
yomineko@鬼畜ヴィタリにゃん💗
74
死体が腐敗してゆく過程を見て修行するために描かれた九相図。どんなに偉い人でも最後は虫や動物に食い荒らされて朽ちて行くだけ。。。雅やかなタッチで描かれているが当時はさぞ衝撃的だっただろう。背景が黄土色なので血が余計鮮明に見える。2023/10/13
ねこさん
17
現代は、死が遠い。故に人の顔を見る時、何時からか頭蓋骨を想像するようになった。自他に求める六つの欲(色、形容、威儀、言声、細滑、人相)を脱落させ、自他の肉体に対する執着を断ち切るよすが、九相図。仏道に帰依する者が、イメージでしかない死を冥想によって自らの身体に落とし込む。時に『摩訶止観』に基づく冥想の一つ九相観においては、実際の死体を見たという。九相図を寄進し衆生の発心を促すことが善行、懺悔の証となること、季節の移ろいと共に無常感の表出として描かれたという点が、中世富裕層の死生観、我執の質を感じさせる。2024/01/21
MJ
12
「九相図をよむ」を読み、松井冬子の絵に興味を持った。暫く日本画の研究をしてみようか。 追伸 肝心の「九相図をよむ」の感想だが、素晴らしいの一言に尽きる。古今東西、性欲をコントロールするために、人間は様々な工夫を凝らして来たが、死後の姿をステップに分解して想像するとは!嗚呼、人間の業の深さよ。2023/08/05
うさぎや
4
九相図にもいろいろなパターンがあるらしい。色々わかったけど謎もまだ多い。2023/08/12
くまくま
3
高校のときだか資料集に載っているのをみて不気味な印象を抱いたが、仏教修行の目的があったというのは知らなかった。各段階の構図の意味がわかってくると、不気味さよりも何か不思議な魅力をもって見られる。2023/08/13