- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
日本の科学研究のルーツは江戸時代に遡る。
長期に及ぶ政治的安定の中、人々は好奇心の趣くままに蒐集や実験、そして探究に没頭した。
その分野は数学、博物学、物理学、生物学(動物の飼育法や植物の品種改良)、花火や時計等の職人技術と、膨大な範囲に及ぶ。
さらに江戸の人々が熱中した「科学」の中には、今日の我々が失いつつある大切なものが隠れている。
本書ではそうした知の蓄積を丁寧に辿り直し、近代科学とは一線を画す「もう一つの科学」の姿を浮かび上がらせる。
『司馬江漢』『江戸の宇宙論』に続く「江戸三部作」、ここに堂々の完結。
【目次】
はじめに
第一章 和算
日本の数学の簡単な歴史/数学の三分類/「算勘碁知恵阿呆の内」/遊歴和算家/「和算」のその後
第二章 博物誌
本草学から博物誌へ/さまざまな「博物誌」学者たち/博物大名/「紅毛博物学」/私の印象に残った人たち/江戸の博物誌の終焉
第三章 園芸
花卉・花木園芸の歴史/園芸文化の広がり/奇品ブーム/江戸の農業・野菜作り
第四章 育種
鼠/金魚/鳥/虫/蚕
第五章 技術
鉄砲・花火/望遠鏡・眼鏡/時計/からくり
おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takao
4
ふむ2024/06/23
乱読家 護る会支持!
4
江戸時代の役に立たない科学に焦点を当てる本です。 テーマは江戸時代の「数学(和算)」「博物誌の成果」「園芸」「育種」「技術」。 江戸時代の人たちは、好奇心が旺盛で、あそび好きで、凝ると損得を忘れて夢中になる人たちが多かったようですね。 ⚫︎科学の発展には、「時間的余裕」「そこそこの経済力」が必要。江戸時代はその条件を満たす一定数の層が居た。 ⚫︎西洋の科学と違って、東洋の科学は「体系化しない」「人間の視点から」「幅広く、難しくもなく」「近寄りやすい」などが特徴。2024/01/22
なおこっか
3
学者が正誤や有用性を追求するような科学ではなく、好奇心の趣くままに江戸の人々が楽しんできた科学的な事事の話。平賀源内などの有名人はスルー、山片蟠桃の地動説に関心あるのだがその辺もスルー。逆に一般の人々が楽しんだ園芸や金魚等が詳しい。博物誌は机上でやいやい言える武家中心、逆に土をいじって朝顔や万年青(渋い)の変わり種を探るのは職人たち。信州上田の養蚕家、清水金左衛門が湿気の測定器を考え出し、本まで書いているのがまた嬉しい。西洋からのレンズをあっという間に分析した眼鏡、鉄砲が廃れ実用金物にニーズが変わる話も。2025/02/19
とりもり
3
面白かった。「科学」と銘打たれているが、あくまで江戸の人たちは自分たちの好奇心を満たすために色々な知識を深掘りしただけなので、「学問」としての網羅性や体系はない。その点が西洋科学との最大の違いであり、部分的には非常に高度な面がありつつも、全体としてのレベル差が大きく開いた最大の理由としている。その通りだと思う一方、和算のようにこれだけ市井の人々が夢中になったという江戸庶民の知識レベルの高さは、改めて再評価する価値があるかと。落語だって、和歌に対する造詣がないとオチが分からない話なんかもあるしね。★★★★☆2025/01/08
HH2020
3
◎ 第一章和算から博物誌、園芸、育種と続き第五章技術まで、江戸時代に流行ったことがらを科学と結びつけて読み解く。当初、和算と技術が私の興味の対象だったのだが、読んでみれば博物誌、園芸、育種も同等またはそれ以上に面白かった。好奇心、変わり物、自然への慈しみ、通、芸、粋、奇、怪、などなどがキーワードに挙げられよう。現代のわれわれの科学に比べ、江戸時代の科学は「遅れた科学」ではなく「もう一つの科学」であった、という著者の論にすとんと納得した。先に読んだ渡辺京二の『江戸という幻景』に呼応したものを感じた。2023/10/11
-

- 電子書籍
- 日商簿記2級 光速マスターNEO 工業…
-

- 電子書籍
- 人形の家【タテヨミ】第4話 picco…
-

- 電子書籍
- noicomi 御曹司は幼なじみを独り…
-
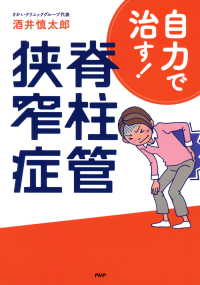
- 電子書籍
- 自力で治す! 脊柱管狭窄症
-
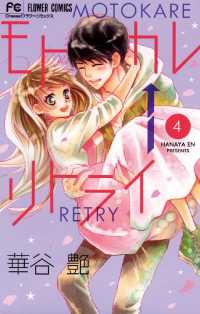
- 電子書籍
- モトカレ←リトライ(4) フラワーコミ…




