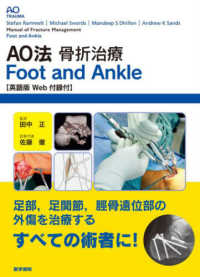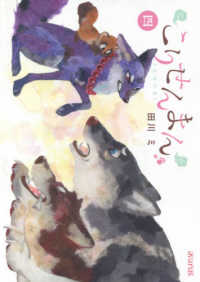内容説明
「役立たず」は「役に立つ」。自分を磨きたければ、無用の「知」に挑め。世界32カ国22言語で翻訳出版されたベストセラー。実用主義・効率主義がまかり通る現代への痛烈な批判。
無益さにこそ価値がある!
役に立たない文学や芸術を愛せる人間になるために!
グローバル経済、利益中心、効率優先……大切なものはどこへ行った?
錚々たる古の文人・思想家の言葉をたどり、生きる意志を再発見する。
世界32カ国で刊行された大ベストセラー!
――過去の記憶、人文科学、古典語、教育、自由な研究、想像力、芸術、批判的思考など、人間のあらゆる活動を後押ししてきた文明の息吹が、徐々に根絶やしにされようとしている。
――食事や呼吸を必要とするのと同じように、わたしたちは「無駄(役に立たないこと)」を必要としている。
――真に美しいものは、なんの役にも立たないものだけである。役に立つものはすべて醜い。
……わたしは余計なものを必要とする人間だ。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
114
イタリアの大学教授が、役に立つか(利潤を生み出すか)どうかで学問を選別する世相に警鐘を鳴らす。古典や文学を軽視し、原典を読まずに手引き書で間に合わせる風潮を憂う。「学生はお客様」などとする大学の姿勢を批判し「教育は無私と無償の精神」との原点回帰を訴える。日伊共通の著者の悩みに全面的に共感する。ただ「役に立たないものが、実は役に立つんだ」という論法には異議がある。それだとやっぱり「役に立つことが大切」ということにならないか。純粋に「知の営みそのものが楽しい」でいいではないか、役に立たなくても。甘いかなあ~。2023/04/27
ATS
11
古今東西の小説や哲学書などの古典を引用し、いわゆる「無用の用」の重要性を説く。個人的には中盤の反緊縮の効能と終盤の愛-知(フィロソフィア)の部分が印象的だった。イタリアでもネオリベの流れで緊縮により教育や文化継承などが蔑ろにされているよう。真理を所有してはいけない。所有したとき科学は歪んだ宗教と化し、盲信は寛容を殺し社会を狭小化して殺伐とさせる。余剰(余裕)が社会の安定や人間性を育んでいるような気がしている。ギリギリのマンパワーではコロナ対応はできず、金儲けに走れば芸術はすたれる。やや退屈な部分もある。2023/04/10
ichigomonogatari
4
無用なように見えるけれど実はこんなに効用があるんですよ、と、たくさん例をあげて説明する本かと思って読んだら全く違って、一見実利に役に立たなさそうな文系だけど、実は人が生きていく上でても役に立つ、ということを明らかにしようとするアンソロジー。知・真理を追求することは、自分と異なる価値観や文化の他者との共生の道へ通じるという。文系は役に立たない、そこが良いとか世界に役に立たないものはないとか、引用されている古典を見ると文系は昔から役に立たないと言われ続けてきたことを改めて知った。2023/09/30
bibliotecario
3
様々な古典を引用し、実利主義を批判する本。グローバリズムや新自由主義という怪物が跋扈する現代で、このような本が多くの国で翻訳され版を重ねているのは一筋の光でしょうか。2023/05/06
斉の管仲
3
心が洗われる本。今の学問のあり方を問うているが、私の周りには、このような考えの人は全く居なくなった。私は年を取ってしまったのか?2023/02/27
-
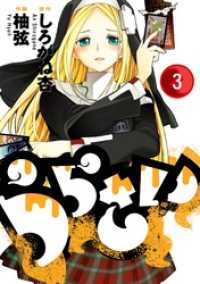
- 電子書籍
- うらさい 3巻 ヤングガンガンコミックス