内容説明
支援の現場で出合う暴力は,本質的には防止や制圧をするものではなく,クライエント自身が主体的選択として「手放す」ものである。しかし,クライエントは欲求や感情を言葉ではなく暴力という対処行動として表出し,そのことに苦しむ場合でも自ら援助を求めることはほとんどない。なぜなら,援助を求めるとは欲求や感情を言葉で表出することそのものだからである。その結果,暴力を振るうクライエントへの支援は困難を極めることになる。
本書では,暴力の定義,起源,要因を解説し,医療・司法・福祉各領域におけるDVや児童虐待への支援実践を概観しながら,思春期以降の児童から成人までを対象とした暴力を手放すための四つのフェーズからなる支援モデルとセラピストの適切な「ありよう」を提示する。
また,児童による性暴力と施設における暴力についての支援モデルを適用した二つの事例と,最終章で著者が提言する「情理の臨床」を通して,暴力を手放す臨床心理学的支援に迫る。
目次
序文|田嶌誠一
はじめに
第1章 手放す支援の難しさ
第2章 暴力の起源を辿る
第3章 暴力が生じる要因とその影響
第4章 各領域の支援を概観する―医療,司法,福祉を中心に
第5章 DVと児童虐待の支援を概観する
第6章 手放す支援のモデル
第7章 セラピストのありよう
第8章 事例を通じて理解を深める(1)―性暴力の事例
第9章 事例を通じて理解を深める(2)―施設における暴力
最終章 「情理の臨床」としての手放す支援
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひろか
9
いやー、しびれました。児相職員をしつつ、論文を書くこと自体がすごい。児童福祉領域から、臨床心理学を捉え直す。2023/05/04
saiikitogohu
1
「介入役割と支援役割」という、それぞれが困難なだけでなく、相矛盾する役割を背負わさている日本の児童相談所における実践から生まれた実践理論が筆者の言う“暴力を手放す支援”である。それには「暴力を止める」「足場をつくる」「支援する」「定着を助ける」という四つのフェーズがある(83)。とりわけ独特なのが、フェーズ0の「暴力を止める」における、【止める同意を得る】【支援の文脈を示す】ということ。最初に法律システムの語彙でもって、かなり具体的に暴力を止める同意をもらうのが大切とのこと。要は枠設定は必須。2024/11/29
-
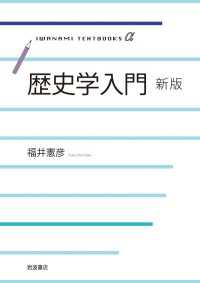
- 電子書籍
- 歴史学入門 新版 岩波テキストブックスα
-

- 電子書籍
- みんな私のこと「かわいい」って言ってく…
-

- 電子書籍
- ストーカー浄化団(5)
-

- 電子書籍
- 「すし」神髄 杉田孝明
-
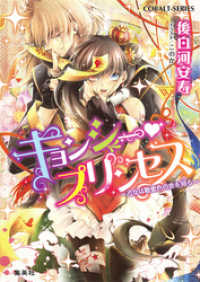
- 電子書籍
- キョンシー・プリンセス ~乙女は糖蜜色…




