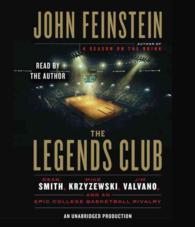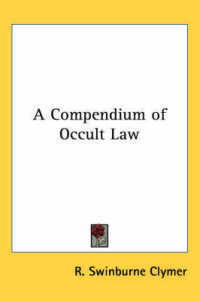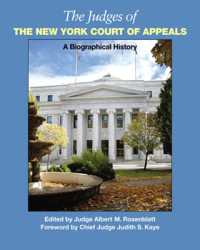内容説明
ときは明治、蒸気機関車が煙をあげてはしっていた時代です。東海道本線からはずれてしまった小田原―熱海間を、人が押してはしる鉄道がありました。海べの道にしかれたその人車鉄道は、景色もよく、がたごとのんびり、風情があったそうです。その後その道は、軽便鉄道がはしり、東海道本線となり、新幹線がはしる路線へと変わっていきます。130年前から現代まで、海べの道を定点に、見て楽しいパノラマ交通発達史。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぶち
101
読友さんのレビューで手に取りました。幼い頃、祖母や母に連れられて熱海には毎年のように行っていました。東海道本線に乗って行ったのですが、小田原--熱海間に人が推して走る鉄道があったなんて、まったく知りませんでした。人が歩くのと同じくらいの速度なので景色をゆっくりと楽しむことができたそうです。晴れの日は気持ち良いでしょうが、雨の日は大変でしたでしょうね。車輛を押す人は苦労が多かったと思います。たくさんの人や物資が猛スピードで行き交う新幹線の時代になりましたが、人道鉄道の光景もまた素敵だろうなぁとも思います。2021/09/19
やま
80
まさか人が箱に入って、人が押す鉄道があったとは。小田原から熱海まで、人力車から始まって、東海道新幹線が走るまでの歴史を解りやすく描いた絵本です。いまから130年以上前の明治22年(1889年)、東京の新橋から神戸まで、東海道本線が開通しました。ところが鉄道は、現在の海沿いを通る路線ではなく、箱根山の向こう側の御殿場を通るルートを走りました。海から外国の艦船に砲撃されないよう、また海沿いの険しい地形を通らずにすむよう、安全なコースを選んだからです。続く→2021/07/17
ヒラP@ehon.gohon
35
昔東海道は御殿場線経由だったことは、かすかに思い出しました。 それにしても、トンネルが出来て熱海から山を抜けていけるようになるまでの交通手段には驚きました。 人力車、馬車鉄道、人車鉄道、軽便鉄道と信じられない歴史には圧倒されました。 今の当たり前が、数々の苦労を経て築かれたことを、実感する一冊でした。2021/08/02
クラムボン
27
小田原-熱海間の鉄道物語です。明治22年に東海道本線が開通。しかし箱根エリアは御殿場経由の北廻り。小田原も熱海も路線から外れた。そこで元々国府津から小田原経由で箱根湯本まで走っていた馬車が、レール軌道の《馬車鉄道》になる。新たに小田原-熱海間は《豆相(ずそう)人車鉄道》が開通した。人車鉄道とは、4~8 人乗りの客車を2人の車夫が押す。登り坂では客は降り、時には客車を押した。脱線転覆の時は、乗客が客車を持ち上げレールに戻したりと、のどかな時代だった。イラストがわかり易く楽しい絵本です。2021/09/05
shiho♪
23
鉄道大好き長男と。今の御殿場線が最初に開通した東海道本線だったとは、初耳でした。そうすると温泉地である小田原や箱根、湯河原、熱海は鉄道から取り残されてしまいます。そこで作られたのが『豆相人車鉄道』。馬車鉄道は知ってましたが、人車鉄道というのも初耳。海沿いで景色も良かったとの事で、車夫に車両を押してもらってそれはそれでとても贅沢な熱海への旅だったと想像します。 新幹線で一瞬で通り過ぎてしまう熱海周辺ですが、丹那トンネルを含め歴史を知ると、ゆったり寝て過ぎるのももったいない気がしますね。2021/10/22
-

- 電子書籍
- 愛は喝采に包まれて【分冊】 12巻 ハ…