内容説明
フィクションの世界で描かれる「暗黒の中世」は,近代ヨーロッパが創り出した政治的な物語だ.異端審問,王の儀礼,市民の裁判……注意深く史料を読み解けば,当時の人びとが生き生きと甦る.『歴史〈一冊でわかる〉』やBBCの企画,市民向け講座で有名なケンブリッジ大学教授が誘う,新鮮でドキドキする本格的中世史入門.
目次
第二版への序文
序文と謝辞
地図
第1章 中世を枠付ける――リアルとフィクション
とある中世的な話
中世主義と史学史
フレーミング(枠付け方)の政治学
第2章 中世を追跡する/史料と痕跡
多声音楽か? 不協和音か?
校訂版と文書館史料アーカイヴズ
文書を使うこと
年代記
証書
図像イメージ
法史料
第3章 中世を読み解く――隣接諸学との協働
人類学
数字と統計
考古学・科学・物質文化
テクストと文化論
第4章 中世を議論する――深まる論点
儀礼
社会構造
グローバリズム
文化的アイデンティティ
権力
第5章 中世を作り,作り直す――「中世主義」再考
訳者あとがき
注
中世をより深く知るための読書ガイド
索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
15
ちょっと思っていたのと違った一冊。イギリス人の中世史家による「中世史家ってこういう仕事なんだよ」という紹介みたいな内容。ギリシャ・ローマの栄光と輝かしきルネサンスの間にある暗黒時代という認識から生まれた時代区分「中世」を研究するヨーロッパ人の苦悩は、日本人が思っているより深い模様。史料の扱い方、人類学や考古学など隣接する学問との向き合い方などは、歴史家の職人としての部分が見えて興味深い。まぁ一番面白かったのは、イギリスやフランスなど各国の研究者を比較して述べた俗っぽいところなんですねどね。2023/02/04
takao
2
ふむ2023/07/18
plum
0
歴史する(doing histry)ために枠付ける(frame)入門書。中世の文化,政治,社会が特定のテクストにどのような影響を与えているかを知ることで,歴史家はさらに豊かな資源を得るp60。資本主義の近代性;賃労働と市場を基盤とした経済は,かなり遡る必要があるp106。人種の移動(DNA),識字率,権力;税・ネイション,信仰の時代→宗教改革以前のキリスト教の中世的な性質(慣習や期待の念というより深い部分での異教時代からの連続性の保存)。2023/03/02
kinaba
0
どちらかというと「中世史を研究する行為とは何か」というか「中世史家とは何か」といった趣の本だった。少なくとも通俗的には間に暗黒の時代を挟んでいることになっている、という歴史観は日本にいると馴染みがあまりないので、なるほどそうなのかという思いと、そこで目を曇らせすぎないためのスタンスみたいなものをどう捉えたものかという思いと。 2023/01/29
-

- 電子書籍
- 悪役令嬢がポンコツすぎて、王子と婚約破…
-
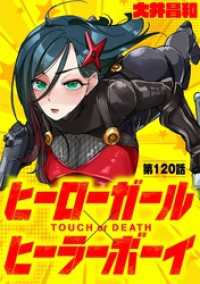
- 電子書籍
- ヒーローガール×ヒーラーボーイ ~TO…
-
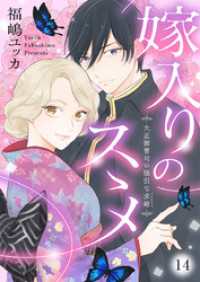
- 電子書籍
- 嫁入りのススメ~大正御曹司の強引な求婚…
-
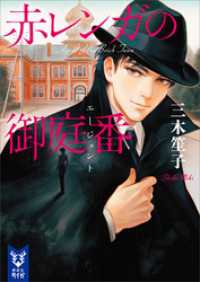
- 電子書籍
- 赤レンガの御庭番 講談社タイガ
-

- 電子書籍
- どんなときでも自信があって、自由で、美…




