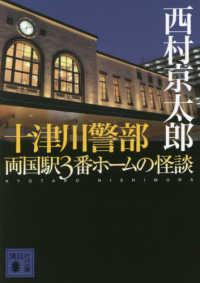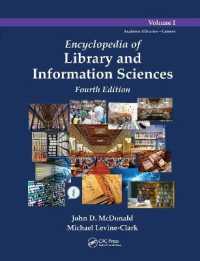内容説明
「その意見って、客観的な妥当性がありますか?」。この感覚が普通になったのは、社会の動きや人の気持ちを測定できるように数値化していったせいではないか。それによって失われたものを救い出す。
目次
はじめに/第1章 客観性が真理となった時代/1 客観性の誕生/2 測定と論理構造/第2章 社会と心の客観化/1 「モノ」化する社会/2 心の客観化/3 ここまでの議論をふりかえって/第3章 数字が支配する世界/1 私たちに身近な数字と競争/2 統計がもつ力/第4章 社会の役に立つことを強制される/1 経済的に役に立つことが価値になる社会/2 優生思想の流れ/第5章 経験を言葉にする/1 語りと経験/2 「生々しさ」とは何か/第6章 偶然とリズム──経験の時間について/1 偶然を受け止める/2 交わらないリズム/3 変化のダイナミズム/第7章 生き生きとした経験をつかまえる哲学/1 経験の内側からの視点/2 現象学の倫理/第8章 競争から脱却したときに見えてくる風景/あとがき/注/参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
141
客観性を求めることは確実性を求めることでもある。とすれば、この点へのこだわりは、不安の裏返しではないだろうか。しかしそこにマジョリティの視点への偏向、マイノリティの排除に結びつく危険が潜んでいるとは、なかなか気がつかない。社会においては、統計こそ客観的という考え方も、個別の事例を見えなくする。苦悩や貧困のつらさなどを、数値化しようということ自体に問題があることは誰でもわかる。ではどんな方法がありうるか、実社会を考えるには、どんな思考が必要かを紹介。自然科学への批判ではなく、新しい方法へのアプローチである。2023/12/16
けんとまん1007
140
確かに、「客観的に・・」というフレーズに触れることも多い(表現はいろいろあるが)。改めて、それを考えるきっかけになった。一見、正しいようであって、果たしてそうなのかと考える。100%そうなのか、概ねそうなのか、半分くらいなのかなど、実は、曖昧なままということを考える。それを補うエビデンスも同じことが言えるかもしれない。その陰に隠れてしまう、隠されてしまうことへの視線が大事。個が消されてしまうこと、それを押し隠してしまうことの危うさもある。やはり、一つ一つの物語へのこだわりを捨てないこと。2023/10/16
どんぐり
94
エビデンスや数値化された客観性を追求すると、「私はこう感じる」「私はこうした」という経験がもつ価値が切り崩されていく。そのことを問題視しながら、いかに人間の体験を尊重し、相手の話を丁寧に聴き取るか、現象学の立場から論じた本。前半部が客観性と数値化がもたらす弊害。後半部がケアの場を題材にして患者が経験を伝える語りに着目した現象学の思考法を紹介している。YAの読者には残念だが、これは臨床哲学に類する本だ。ちょっと小難しい。2023/12/01
ムーミン
90
現在手がけている様々な施策を考え、進めていく上で、欠かしてはならない個別のエピソードに意識を傾けることを確認できました。2024/04/29
ネギっ子gen
75
【社会的な困難の中にいる人、病や差別などに苦しむ人たちの声を尊重する社会に――】数値化で失ってしまったことを問い直し、客観性や数値を盲信することに対して警鐘を鳴らした書。巻末に、注と参考文献。<一人ひとりの顔と声から出発して社会を作ること、そのような社会をモデルとして大きな制度を考えること、ヒントは、西成のように困難が集積した地域にこそあるのではないか。というのは、そこでは制度的な支援だけでは生存と安全を保障できないがゆえに、目の前にいる一人ひとりの顔と声を起点としてコミュニティを作ってきたからだ>と。⇒2025/06/16
-

- 電子書籍
- 男子禁制ゲーム世界で俺がやるべき唯一の…
-
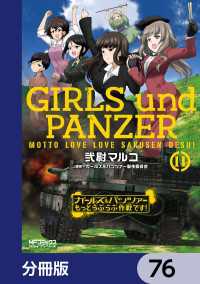
- 電子書籍
- ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作…