内容説明
ドゥルーズ=ガタリ、メルロ=ポンティ、サルトル、モース、デュルケム、ヴィヴェイロス・デ・カストロ、デスコラ、ストラザーン――いずれも「自然」をめぐり、レヴィ=ストロースの神話論理の再解釈や「構造」の捉えなおしとして進行してきた哲学と人類学について、思考様式の違いや歴史的な影響関係、主題の反復を浮き彫りにする。
目次
はじめに
第1章 自分自身の哲学者になること――文化人類学と哲学が交錯する場所で[山崎吾郎]
1 ともに生み出される人類学
2 自然と文化のねじれた関係
3 形の論理――神話、制度、技術
4 形の変化、具体の科学
5 自分自身の哲学者になること
第2章 他者の認識と理解――「ネイティヴ」・文化・自然をめぐって[磯直樹]
1 はじめに
2 ネイティヴの視点から
3 ヴェーバーの理解社会学
4 多文化・単一自然主義を超えて――デスコラの「自然の人類学」
5 ブルデューとサヤドの反省性
6 おわりに
第3章 メラネシアからの思考――ストラザーン『贈与のジェンダー』における「行為」と「産む身体」をめぐって[里見龍樹]
1 メラネシアからの思考
2 ストラザーンの「関係論的人格」論
3 『贈与のジェンダー』における「人格」と「行為」
4 メラネシア民族誌の系譜
5 『間に立つ女性たち』の行為論
6 フェミニスト人類学と「産む身体」
7 「メラネシア的社会性」の理論
8 パイエラの少年たち
9 「美学的な罠」
10 産む身体
第4章 神話の精神分析/呪術のスキゾ分析――『千のプラトー』における人類学と人類学もどきの活用について[山森裕毅]
1 はじめに
2 精神分析と人類学
3 狼はただの一匹か、それとも数匹か
4 精神分析の何が有害か――『千のプラトー』における精神分析の捉え方
5 逃走のための概念群――群れ、多様体、生成変化、強度
6 D-Gと人類学/人類学もどき
7 呪術と呪術師
8 動物になるとはどういうことか――同盟、伝染、群れ、変則者
9 薬物と知覚――動物への生成変化のその先へ
10 アルトーとペヨトル・ダンス
11 結びに代えて
第5章 生成する構造主義――フィリップ・デスコラと野生の問題[小林徹]
1 はじめに
2 構造人類学の方法論
3 野生の構造主義/野生の存在論
4 構造存在論
5 おわりに――構造主義の生成
第6章 構造とネットワーク――レヴィ=ストロース×ラトゥール[久保明教]
1 歪な鏡像
2 人間ならざるものはいかに人間になるのか
3 人間ならざるものはいかに行為するか
4 構造のネットワーク
5 ネットワークの構造
6 ノーマンズランド
第7章 レヴィ=ストロースにおける階層と不均衡[近藤宏]
1 はじめに
2 「絶えざる不均衡」をめぐって
3 階層をめぐって
4 おわりに
第8章 レヴィ=ストロースの哲学的文脈――構造と時間/自然と歴史[檜垣立哉]
1 はじめに――レヴィ=ストロースは哲学者なのか
2 レヴィ=ストロースの複合性
3 レヴィ=ストロースにおける「出来事」と「構造」
4 「再びみいだされた時」としてのチューリンガ
5 サルトルの『弁証法的理性批判』との対比
6 「マナ」をめぐって――ドゥルーズとデリダ
7 デリダとレヴィ=ストロース
8 ルソー主義者レヴィ=ストロースへの批判
9 レヴィ=ストロースはどこへ開かれるのか
第9章 デュルケムはパンドラの箱を開けたか――思考の非個人主義と非人間主義[近藤和敬]
1 哲学と人類学のすれ違い――哲学の近代性と思考の個人主義と人間主義の問題
ほか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
PETE
文狸
-
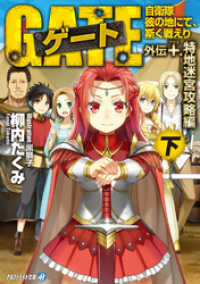
- 電子書籍
- ゲート外伝+<下> 自衛隊 彼の地にて…








