内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
「でない」、「かつ」、「または」それに、これらから派生する「ならば」などは、特別な知識ではなく、ごく普通の人がごく普通に思考するうえで、極めて大事な言葉です。日常会話レベルでは、その意味の解釈が個人によって多少曖昧でもトラブルは発生しないかもしれません。また、曖昧性のために日常会話がかえって円滑に進むこともあります。しかし、様々な人が混在している複雑な社会では、「でない」「かつ」「または」「ならば」などの基本用語について最低限の共通認識は必要です。基本をしっかり押さえていればこそ、安心して曖昧さを受け入れることができます。本書では、表とベン図を使って、読者が論理学と集合の基礎知識を身につけられるように解説していきます。
-

- 電子書籍
- 魔王様は逆ハーレムが嫌い【タテヨミ】5…
-
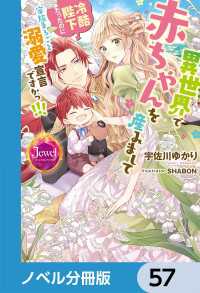
- 電子書籍
- 異世界で赤ちゃんを産みまして 冷酷陛下…
-
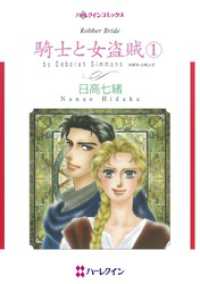
- 電子書籍
- 騎士と女盗賊 1【分冊】 10巻 ハー…
-
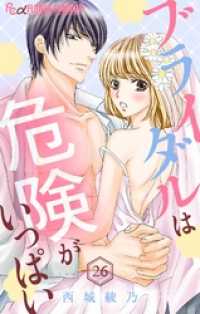
- 電子書籍
- ブライダルは危険がいっぱい【マイクロ】…
-
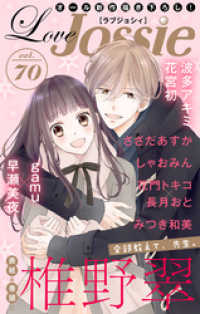
- 電子書籍
- Love Jossie Vol.70 …



