内容説明
2度の世界大戦で英国が実施した長距離封鎖は合法だったのか。そして、海上封鎖は現代でも有効な海戦の方法であり続けているのか。この2つの疑問が本書の出発点となっている。
本書の主たる分析対象である海上封鎖は、戦時に敵国通商を遮断する海戦の方法の1つであり、主力軍艦同士の砲撃戦のような華々しいものではなく、軍艦が商船を停船させ船内を捜索するような地味な戦いの累積である。一方、敵国港には様々な国の船舶が出入りして貿易が行われているため、敵国商船のみでなく、これら全てを統制する必要が生じる。
戦時の敵国通商は、交戦国以外には自国繁栄に必須である一方、他方交戦国には敵国戦力を増大させ敗北の原因となり得る存在である。すなわち、戦時通商の問題は、一方では「海洋は戦時にも万人共通の利用に供される」との主張に、他方では「戦時には交戦国は敵国通商を遮断する権利がある」との主張に支えられている。両者の対立の結果、均衡点に海上封鎖と海上捕獲の2つが成立した。前者は全ての船舶・貨物の没収を認める代わりに実施海域を制限し、後者はあらゆる海域での措置を認める代わりに対象船舶・貨物の国籍・種類を制限する。本書は前者を分析対象とし、海上封鎖がいかなるもので法的にいかに説明し得るかを分析し、その現代的意義を考察する。
海上封鎖はいかなる条件の下で許容されるかが、常に論争の焦点になってきた。その条件は、それぞれの時代の海戦と海運をめぐる環境の変化の影響を受けて常に変化してきたが、一方で一貫して実効性という概念で説明されてきた。実効性とは、実際に通航を阻止できる兵力の配備を伴って初めて海上封鎖が合法となるというものであり、国家実行の蓄積の中で徐々にその性質が明らかとなってきた概念である。実効性は1856年のパリ宣言及び1909年のロンドン宣言に明文化されたが、両宣言を中心とする封鎖法が、近接封鎖、すなわち、被封鎖沿岸の近傍に封鎖兵力を配備する海上封鎖を要求していたのか、又は、長距離封鎖、すなわち、封鎖沿岸から相当に離れた位置で実施される海上封鎖を許容していたかは、論争が続いている。
さらに20世紀に入ると、海戦及び海運環境の変化、交戦国側の主張の優勢及び第2次大戦後の戦争違法化といった新たな状況が出現し、海上封鎖の実施にいかなる影響を及ぼしているかが明らかでない。これら状況が封鎖法を変化させたか否かについては、元々の封鎖法が近接封鎖を要求していたのか否かで異なる。
これらの問題が明らかでないために、現代の海上封鎖がいかなるもので、法的にどのような説明が可能であるかは明らかではなく、さらには現代では海上封鎖は検討に値する海戦の方法ではなくなったと評する多くの論者が登場した。
本書は、17世紀以降今日に至る国家実行、判例及び学説を網羅的に分析して長距離封鎖の合法性を評価するとともに、20世紀以降に生起した状況が及ぼした影響の観点から封鎖法を捉え直し、その現代的意義を明らかにし、過去及び今後設定される海上封鎖に統一的な評価基準を提供しようと試みたものである。
目次
序章 ―問題の所在―
1 現代の封鎖法に残る不明確性
2 海上封鎖の捉え方に関する見解対立
3 本書の目的、意義及び構成
4 用語法
第1 部 海上封鎖の実効性の理論分析
第1 章 海上封鎖の概念
第1 節 海上封鎖の特徴
第2 節 類似措置との相違
第3 節 小括:本著における海上封鎖の定義
第2 章 海上封鎖の中心的要件たる実効性
第1 節 海上封鎖の実効性の法的性質
第2 節 海上封鎖の実効性の意義
第3 節 妥協理論の妥当性
第4 節 小 括
第2 部 黎明期からロンドン宣言に至るまでの海上封鎖の実効性
第3 章 黎明期から第2 次武装中立に至る国家実行の蓄積と海上封鎖の大原則の萌芽
第1 節 海上封鎖制度の誕生に至る背景
第2 節 黎明期から第2 次武装中立に至るまでの海上封鎖をめぐる環境
第3 節 海上封鎖を規律する大原則の萌芽
第4 節 第1 次武装中立における碇泊封鎖の明示
第5 節 第2 次武装中立における武装中立同盟側の敗北
第6 節 小 括
第4 章 パリ宣言における実効性の原則の明文化
第1 節 ナポレオン戦争からパリ宣言に至る海上封鎖の概観
第2 節 19 世紀中葉における木造帆船時代の終焉
第3 節 19 世紀前半から中葉にかけての実効性に関する判例の蓄積
第4 節 パリ宣言における実効性
第5 節 小 括
第5 章 ロンドン宣言における封鎖法の完成
第1 節 南北戦争からロンドン宣言に至る海上封鎖の概観
第2 節 判例蓄積を通じた実効性概念の解明
第3 節 海戦の中核としての水上艦の地位の継続
第4 節 ロンドン海軍会議を通じた実効性概念の解明とその限界
第5 節 小 括
第3 部 海上封鎖の地理的限定の現代的様相
第6 章 両次世界大戦における長距離封鎖が封鎖法に及ぼした影響
第1 節 両次世界大戦における海上封鎖をめぐる状況
第2 節 両次世界大戦での海戦環境の激変
第3 節 両次世界大戦中の近接封鎖事例における実効性
第4 節 第1 次世界大戦の長距離封鎖
第5 節 第2 次世界大戦の長距離封鎖
第6 節 小 括
第7 章 海上封鎖をめぐる第2 次世界大戦後の新展開
第1 節 第2 次世界大戦後の海上封鎖をめぐる状況
第2 節 長距離封鎖の必然化と海上捕獲実施上の課題の出現
第3 節 交戦国側の主張の優勢が海上封鎖に及ぼす影響
第4 節 戦争違法化が海上封鎖に及ぼす影響
第5 節 海上封鎖の可能性がある第2 次世界大戦後の国家実行
第6 節 武力紛争非当事国船舶への干渉が許容される範囲を示す国家実行
終章 ―封鎖法の現代的意義―
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
BLACK無糖好き
蟹
畝傍
rineoskiss
-
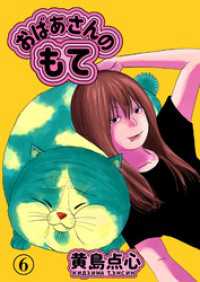
- 電子書籍
- おばあさんのもて 第6話 Comic …
-
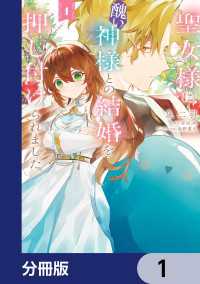
- 電子書籍
- 聖女様に醜い神様との結婚を押し付けられ…
-
![My First DIGITAL『美味しんぼ』名品集 (5)[五臓六腑に染みわたる、あったかおでん編] My First DIGITAL](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1320082.jpg)
- 電子書籍
- My First DIGITAL『美味…
-
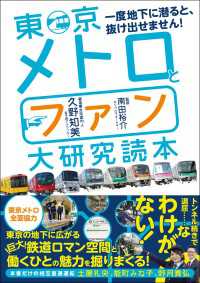
- 電子書籍
- 東京メトロとファン大研究読本
-
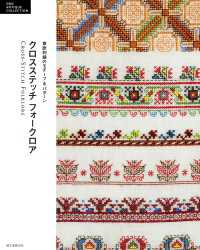
- 電子書籍
- クロスステッチ フォークロア - 東欧…




