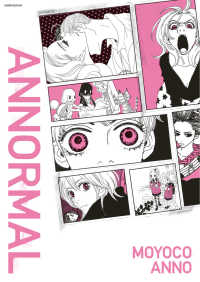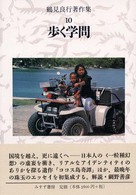内容説明
〈北海道から九州まで〉
古代薫る地を往き、食べた、〝原日本?の風景と暮らしに迫る異文化食紀行
----------------------
蕨(ワラビ)/ 蕗(フキ)
屈(コゴミ)/ の木(タラノキ)
薇(ゼンマイ)/ 蕗の薹(フキノトウ)
栃の実(トチノミ)/ 孟宗竹(モウソウチク)
行者大蒜(ギョウジャニンニク)/ 山葵(ワサビ)
若布(ワカメ)/ 天草(テングサ)
海蘊(モズク)/ 茗荷(ミョウガ)
杉菜(スギナ)/ 銀杏(ギンナン)
二輪草(ニリンソウ)/ 大姥百合(オオウバユリ)……
農耕以前よりこの国で食べられてきた野草や海藻。
「栽培作物」にはない、その滋味あふれる味わいと土地ごとの記憶をたどる旅が、今はじまる。
----------------------
日本の豊饒な自然に触れることで、食料を大切にしたいと思えるし、ささやかな料理の楽しみが味わえる。こうした気持ちは栽培食物からはまず得られない。(「はじめに」より)
〈和歌の世界に誘われながら、時空を超えた食の旅へ〉
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Aya Murakami
94
種をあやすの裏紹介。図書館本。 ツクシ、ワラビは子供のころから家族と採取、料理してきた(ただし、同じ学校の反自然な児童にからかわれた)ので読んでいてなんだか懐かしい気持ちにもなりながら、アイヌの歴史では和人の罪悪感の気持ちにもなる重厚な内容でした。 山から海へと幅広いフィールドから食べ物は得られる今でいう野食の本。アイヌにとっての火の女神はマイエレメント、ヒープリ、ヘスティアを連想。2023/11/05
J D
68
なかなか刺激的な読書となった。山菜や海藻が食べられてきた意味。そこにあった日本の文化。日本人の自然に対する意識がどう育まれてきたのか、山を海を守り、大切にすることで食を生命を守る。そんなことに改めて気付かされた。山菜は、古代から日本人の生命を繋いできたが、今や贅沢もしくは消え去りつつある食文化なのか。最終章でアイヌの食文化に触れているのがこの本の幅を広げている。これから、海藻や山菜を食する度にこの本を思い出すことになりそう。万葉集の引用が語られる食文化に重みを与えていた。2023/05/29
たまきら
48
アメリカ人ライターによる「日本の食材って面白い!」なレポートです。著者の純粋な驚きが伝わってきて、ほほえましいな。アメリカの食材だって、アメリカインディアンの食材や南米料理を見れば多様だし、日本だって決まりきったレシピしか食べない人には山菜は未知の領域。食べ物への興味がある人なら、それはもう国籍は不要ということなんだと思います。2023/07/20
yyrn
35
まず、本の装幀が良かった。手に取って読んでみようという気になったし、中の章立ても、イラストも、取り上げられた山菜をつかったレシピも、和歌の引用にも工夫が凝らされていて読みやすく、なかなか良い本だと思った。▼日本に8年間暮らしたアメリカ人女性が滞在中に近所の人に誘われて山菜取りをしたことがきっかけとなって日本の自然食に強い関心を抱き、日本各地を訪れて、その歴史的経緯や今を紹介していくのだが、土地の古老や第一線で活躍している人々へのインタビューだけで終わらず、多数の文献に当たり、洋の東西の対比ばかりでなく⇒2023/06/03
to boy
25
米国ジャーナリストが日本に滞在して各地の天然植物、海藻などの食文化を楽しんだ記録。栃の実、わらび、わかめなどが日本の昔からどのように食されてきたのか詳しく記載。天然植物は基金などによって栽培植物が不作に食べる非常食(まずい、手間がかかるなど)としての意味と、その季節に少ししか採れない貴重で贅沢な物としての意味とあると言う見解が面白い。アイヌを語った章では倭人たちの暴挙も語られていて悲しい。アメリカ先住民もそうだが、古代日本人、アイヌ人たちは天然植物をうまく利用していたことが分かった。2023/12/07