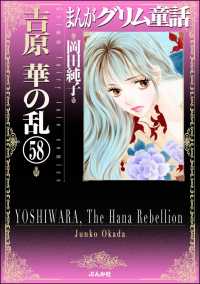- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
読書猿氏推薦! 忙しさや生産性、新しさという強い刺激に駆り立てられる現代において、自分の生きる時間を取り戻すための方法論として素朴な多読ではなく、本書では「再読」を提唱する。読書するうえで直面する「わからなさという困難」を洗練させ、既知と未知のネットワークを創造的に発展させる知的技術としての「再読」へと導く。「自分ならではの時間」を生きる読書論。
目次
はじめに/第一章 再読で「自分の時間」を生きる/「自分の時間」が買いたたかれている/「独学」志向の現代/時間貯蓄銀行の灰色の男たち/「自分の時間」を生きることは自分と向き合うこと/「情報の濁流」が押し寄せる現代/あなたにとって「良い本との出会い」とは何か/一冊でも多くの本に出会うということ/自分を見つめ直す/多くの本を「読み捨てる」ことは避けられない/再読はセルフケアである/「現状維持バイアス」に抗う難しさ/バンドワゴンと自分との対/第二章 本を読むことは困難である/読書スランプに陥るとき/「言葉の解きほぐし」という行為/書物と権威/読書のためらい/本を開く困難、読み終える困難、孤独になる困難/ひとは本を完全に読むことができない/ためらいを繰り返す/より複雑な「わからなさ」の深み/単純な困難と複雑な困難/「わからなくなること」の深みへ/「語るべき人々」/読書に慣れるということ/第三章 ネットワークとテラフォーミング/バーンアウトする現代人/「強さ 激しさ」と「燃え尽き」/初体験信仰/フラットな読書/ネットワークとしての人間・言葉・書物/スモールワールド効果/『侍女の物語』のネットワーク/「わからなさ」をわかるということ/「わからなさ」の裏に潜ませた何か/ビオトープからテラフォーミングへ/ネットワークの奥へ進み、自分のネットワークをつくる/テラフォーミングとは何か/不毛の惑星を住みやすいものに作り替える/ただそこにあるものを組み合わせていく/第四章 再読だけが創造的な読書術である/読書の創造性と不可能性/創造性とは「組み合わせ」である/「未知のジャンル」に挑むときにこそ再読を/「急がば回れ」の正体/「それがあるかもしれない」と期待すること/古典を再読する/古典とはどういうものか/古典と見なされるにいたった背景/それまで知らなかった「つながり」/ベストセラーを再読する/自分だけの「文脈」を加える/ベストセラー同士のネットワーク/批判的な読みも可能/唯一のルーツはない。あるのは無数のルートだけ/第五章 創造的になることは孤独になることである/「読むこと」と「読み直すこと」には違いがない/カルヴィーノ『なぜ古典を読むのか』/他人の通った道を辿り直す/読むことの二重性/古典を読むときは「解説」は読まない方がいい?/虚構のネットワーク、ネットワークの虚構/魔法としての文学/『ナボコフの文学講義』──まるでほんとうのことのように語る/書物を読むことはできない、ただ再読することができる/『アーダ』──つねに欺く/虚構世界の側から現実世界を夢想する/人生の旅路の疑似体験/松岡正剛「千夜千冊」『多読術』──再読における「開き」と「溝」/シャノンのネットワーク/コミュニケーションと「編集」/情報は容易に壊れるからこそ武器へと変わる/少数派のなかの多数派と少数派/斎藤美奈子『趣味は読書。』──少数派としての読書家/善良な読者と邪悪な読者/ベストセラーを批判的に読む──少数派のなかの少数派のなかの少数派/『挑発する少女小説』──少数派のなかの多数派のなかの少数派/自分が生きていくための環境を再構築する/不確かなネットワークのうえで/孤独を深めることで、孤独ではなくなるという逆説/おわりに/参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
tamami
金城 雅大(きんじょう まさひろ)
vy na
チャー