内容説明
〈小文字の復興〉という視座
2011年夏、ふとしたことで、会津若松市にある大熊町被災者が寄り集まる仮設住宅を訪ねることになった。それから隔週で通うようになって9年―。
その間、あるときは被災者と寝食をともにしながら、またあるときは被災者にとって慣れない雪かきや雪下ろしを手伝いながら、被災者の発する言葉に耳を傾けてきた。
途中で、家族が離散するのにいくつも出会ったし、急に逝ってしまった人を野辺送りすることもあった。出会いと、その何倍もの別れがあった。
被災地の外側では、「忘却」に象徴的にみられるような社会的暴力状況が深くおぞましく進行している。
いつごろからだっただろうか。被災者に寄り添うかたちで、「大文字の復興」ではなく「小文字の復興」を言うことに、著者はある種の空しさをおぼえるようになった。
「小文字の復興」という言葉が被災者に届いていないことを、深く知らされたからだという。
被災者それぞれの「生」に寄り添うということはいかにして可能なのか? 希望の「底」で問い続けた震災10年目の復興論。
-

- 電子書籍
- 異世界帰りの元勇者ですが、デスゲームに…
-

- 電子書籍
- 悪役令嬢、十回死んだらなんか壊れた。【…
-
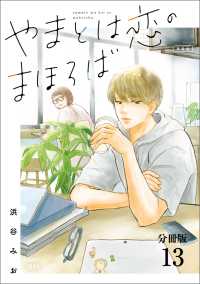
- 電子書籍
- 【分冊版】やまとは恋のまほろば 新装版…
-
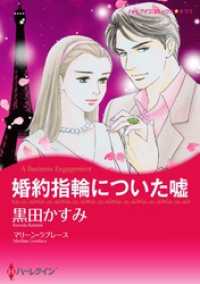
- 電子書籍
- 婚約指輪についた嘘【分冊】 9巻 ハー…
-

- 電子書籍
- 最果てアーケード 分冊版(3)



