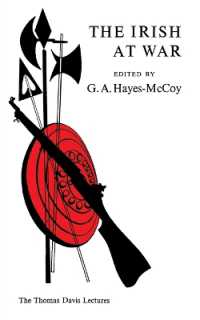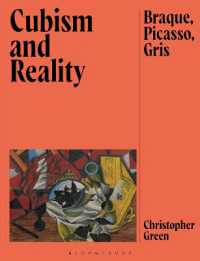内容説明
1985年3月のある晩、ノルウェー北極圏の都市トロムソで、精神科医トム・アンデルセンがセラピーの場の〈居心地の悪さ〉に導かれ実行に移したある転換。当初「リフレクティング・チーム」と呼ばれたその実践は、「二つ以上のコミュニケーション・システムの相互観察」を面接に実装する会話形式として話題となる。しかし「自らの発した声をききとり、他者にうつし込まれた自身のことばをながめる」この会話は、より大きな文脈の探求を見据えた〈開けゆくプロセス〉であった。自らの実践を「平和活動」と称し、フィンランドの精神医療保健システム「オープン・ダイアローグ」やスウェーデンの刑務所実践「トライアローグ」をはじめ、北欧から世界中の会話実践を友として支えるなかで彫琢されたアンデルセンの会話哲学に、代表的な論文二編と精緻な解説を通して接近する。
-

- 洋書
- L'eau de vie