内容説明
明治時代の札幌で蚕が桑を食べる音を子守唄に育った少女が見つめる父の姿。「未来なんて全て鉈で刻んでしまえればいいのに」(「蛹の家」)。昭和26年、最年少の頭目である吉正が担当している組員のひとり、渡が急死した。「人の旦那、殺してといてこれか」(「土に贖う」)。ミンク養殖、ハッカ栽培、羽毛採取、蹄鉄屋など、可能性だけに賭けて消えていった男たち。道内に興り衰退した産業を悼みながら、生きる意味を冷徹に問う全7編。圧巻の第39回新田次郎文学賞受賞作。
目次
蛹の家
頸、冷える
翠に蔓延る
南北海鳥異聞
うまねむる
土に贖う
温む骨
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サンダーバード@怪しいグルメ探検隊・隊鳥
82
(2024-41)明治・大正・昭和・平成の北海道を舞台にした短編集。札幌の養蚕、野付半島のミンク養殖、北見のハッカ農家など、いずれも北海道という厳しい自然の中で続いてきた産業や職業の盛衰が描かれている。表題作「土に贖う」は戦後発展したレンガ産業。ノルマに追われた労働者達の過酷な生産現場は現在の「蟹工船」とも言うべき作品。短編ではあるがどれもずっしりと重く読み応えある小説であった。五つ星です。★★★★★2024/03/22
いたろう
69
表題作他、全7編の短編集。明治時代、札幌・桑園の養蚕業、昭和30年代の別海のミンク飼育業、戦前の北見のハッカ生産、明治時代、鳥島のアホウドリ狩りから北海道に流れついた鳥狩り、昭和30年代の江別の馬の蹄鉄業、昭和20年代の江別のレンガ工場、そして、平成末期の札幌・野幌の陶芸等、かつて北海道で盛んだった産業を中心にした短編集になっている。北見が、かつてハッカで世界一の生産量を誇っていたことを初めて知った。江別のレンガ工場を舞台とする表題作は、主人公の息子の平成の物語に引き継がれるなど、大河ドラマ的な面白さも。2024/07/19
キムチ
67
「肉弾」の受賞後の作品はいかに・・と思い 頁を捲る。北の大地の歴史が果てしない自然と共に眼前に広がる・・背後に消えて行った動植物、産業、そして関わった多くの命と共に。雑誌掲載の7つの短編をまとめた掌品。道に足を踏み入れると目に入る煉瓦、サイロ、厩舎。新政府、屯田兵、殖産興業 とくると雪崩の様に入り込んだ利権業者たちがふった旗の下に養蚕、薄荷、海鳥、煉瓦。。など繰り広げられて行った図が。モノクロ、コマ落としフィルムの様。筆者がこの年齢で物語として再現する筆力は驚嘆するばかり。最後の2編は文芸臭がかなり濃い2024/07/12
piro
54
かつての北海道各地の盛衰を描いた短編集。抗うことができない時代の流れ。容赦無い運命を受け容れ、生き、そして死んでいく。そんな人々の姿を描く河﨑さんもまた容赦無い。『蛹の家』の養蚕、『翠に蔓延る』のハッカ栽培、衰退していく営みに為す術のない人々の姿が悲しい。そしてミンク養殖業を描いた『頸、冷える』はまた違った悲しさに包まれます。でも連作となっている表題作と『温む骨』では弱い人間の確かな強さが一筋の光の様に感じられました。フィクションでありながら確かな存在感を以って紡がれる、地に足が着いた物語でした。2023/04/01
布遊
49
北海道を舞台とした河崎さんの本は、何故か?好き。明治・大正時代の地元に根付いた産業を生業とした人達の短編集。繭とミンクの編が好き。でも、これらのどれも時代と共に衰退していく。アホウドリを殴って捕獲していたことは知らなかった。この時代の人たちの生き方が好きなのかもしれない。2025/08/21
-

- 電子書籍
- 「なむ」の来歴
-

- 電子書籍
- 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見…
-
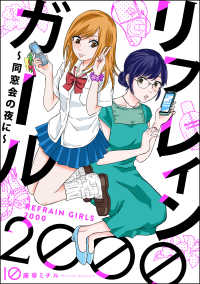
- 電子書籍
- リフレインガール2000 ~同窓会の夜…
-
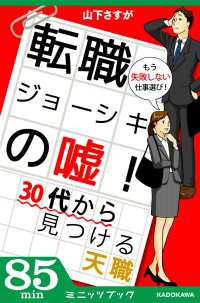
- 電子書籍
- 転職ジョーシキの嘘! 30代から見つけ…
-
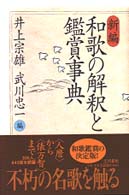
- 和書
- 新編和歌の解釈と鑑賞事典




