内容説明
”平和の誓約”は、なぜ戦争を防げなかったのか?
戦間期の1920年代、当事国としてその構築に密接に関わった国際法秩序から、日本はなぜ逸脱し、戦争へ至ったのか。外交官であり、アジア初の国際司法裁判所所長を務めた安達峰一郎の足跡を手がかりに、国際法の観点から「戦争」と不戦条約との関係をいかに説明できるか、当時の関係者がいかに説明しようとしてきたかを問いなおし、「平和構築に腐心した」知られざる近代日本の姿を明らかにする。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
nagoyan
18
優。半分は戦間期に常設国際司法裁判所裁判所長・判事、外交官として活躍した安達峰一郎の足跡。残りの半分は日本が国際連盟、国際裁判、不戦条約の受容に消極的であったという戦後の通説的見解を検証し、必ずしも日本政府の見解が否定的なもので一貫していた訳ではなかったことを説く。しかしながら、満州事変、日華事変に際しては国際法秩序への整合性を主観的ながらも維持しようと努力していた日本は、「大東亜戦争」段階では、戦間期国際法秩序そのものを「乗り超え」ようとするに至る。今日のロシアの戦後国際法秩序蹂躙を考えるにも良い本。2023/02/11
ぴー
9
不戦条約と安達峰一郎をメインに書かれていた本。安達峰一郎という外交官を初めて知ったが、とても清潔な人だったんだと思った。不戦条約、特に自衛権の解釈次第で、なんとでもなるのかーと感じました。2023/08/27
バルジ
7
「近代」へと足を踏み入れ「一等国」への道を駆け上る最中の国際法受容とその蹉跌、激動する現在の国際情勢における国際法の希望等射程の長い議論を展開する良書。近代日本と国際法受容に関しては外交官・裁判官として活躍した安達峰一郎の視点は、帝国日本の発展と国際社会の中の日本の間で揺れ動く同時代の国際人の典型例であった。不戦条約における「自衛権」の扱いは100年近く経った今でも極めてリアリティのある、現在的な論点である。当時の日本は「自衛権」を幅広く解釈する。戦後はその逆であったがどうもバランスの悪さは否めない。2023/04/09
がんちゃん
4
安達峰一郎は結局、理想と現実の狭間で苦悩した、いち官僚だったということか。ただし理想を掲げることだけでも官僚としては立派な人だったんだなと思いたい。現実に流され己の保身や目先の利害にだけ目にいくのではなく、日本を一等国にすべく、愚かな戦争に突き進んでいった日本に何かしらの理想を説いたことだけは確かだったのだから。とはいえ、ロシア軍によるウクライナ侵攻という現実を前にしたとき、彼が生きた時代と何も変わっていないということに愕然とする。日本もしかり。嗚呼、世界は何もかわりはしないということなのか。2023/06/24
Meistersinger
4
一等国となるため国際法を受け入れてきた日本が不戦条約について欧州の空気を読み違え(日本だけじゃないが)、国家主権の記述という些末事にしか目が向かなかったのだろうなぁ。2023/02/27
-
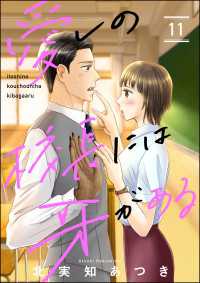
- 電子書籍
- 愛しの校長には牙がある(分冊版) 【第…
-
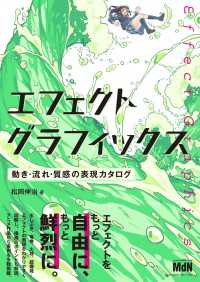
- 電子書籍
- エフェクトグラフィックス 動き・流れ・…
-

- 電子書籍
- 食べることの哲学
-

- 電子書籍
- 新フォーチュン・クエストL(1) トラ…
-
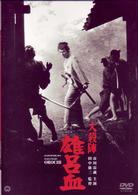
- DVD
- 大殺陣 雄呂血




