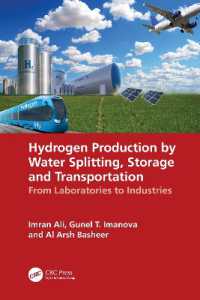- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
街で、庭で、山や森で。花束や食材として。私たちの暮らしの中で、植物を目にしない日はほとんどありません。ところで、そんな身近な草木や花々、野菜や果物は、どうして「その形」をしているのでしょう。葉や枝や根、花や果実が、それぞれどんな理由でいまの形になったのか、豊富な図版をもちいて基礎からやさしく解説する植物学入門。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Major
46
雑草が好きだ。観るだけで学びを得る。名を識るだけで愛着が湧く。何も足さない、何も引かない、馴染みの道端に生う者達。恐ろしく個性的だ。人間など比較にならね。そろぞろが強かに生きている。物言わぬ者達。問いかけは自身に返る。「葉はなぜ平たいのか?」「茎はなぜ長細いのか?」「果実の形は何が決めるのか」自然合目的性に照らし合わせて科学的に自問自答するより他はない。図らずも植物達は僕に哲学もさせてくれた。お薦めです。2024/12/20
PAO
16
「この本で紹介するのは、むしろ興味と知的好奇心に基づいた科学の世界です」…偶々チューリップを育てることになり、その成長を観察してるうちに段々愛着が湧いて可愛くなってしまう毎日…昨日ついに開花して「頑張ったね」と声をかけてしまいました。本当に植物は不思議で動物である私達には理解できない存在なのかもしれませんがこの本を読んで植物への理解がほんの少しですが深まった気がします。桜を愛でる時にも雑草を抜く時にもサラダを作る時にも物言わぬ植物は私達の大切なパートナーであり、彼らの生存戦略には学ぶことが沢山ありました。2023/02/19
ひめぴょん
12
植物の形について「正解」であるかどうかではなく「考える」本。環境の多様性が生物の多様性を生み出している。その多様性がどういう利点のためにそうなっているかを実験や考察を通して見せてくれる。形の背景の意味を考える。分類学とはまた違った視点で面白い。極端な環境ではそれの対応に特化したものが生き残るのに対して、温和な環境ではいろいろな因子への対応を考慮した多様性のある植物が存在する。そういう目で見ると世界が違って見えてくるなあと感じました。以下は文中で気になった部分。 無駄に見える部分でも実際にはなくてはならなら2025/01/13
行加
7
植物の光合成を専門にされている先生の本。院内図書室本。 かつて理科の授業を受けた「大人」に向けた本ですが、植物に興味がある子どもたちにも面白いかもしれません(*^^*) 教科書に載っていた「葉の断面図」の詳しい説明とか、根粒の事とか…当時は暗記するだけだったものを理解できたのは幸せでした(*^^*) かといって、庭の雑草が可愛くはならないので、特徴を頭に入れつつ草刈りに精を出したいと思います!w2025/08/25
kamekichi29
6
植物の形がなぜそうなったかを、考える本。著者が光合成の専門家で形状などについてはあまり詳しくない?ということで、読者も一緒に理由を考えながら、解説していくという感じ。2024/05/29
-

- 電子書籍
- 偽装警官~警視庁極秘捜査班~ 〈3〉