- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
古典を読み味わうことは哲学を学ぶうえで欠かせない。だが、過去に書かれたものを読むという一見受動的にもみえる行為から、どのようにして新たな思想が生み出されるのか。そもそも「自分の頭で考える」とはどういうことだろうか。〈つながり〉という言葉を手がかりに、読書という営みから、本と本のつながり、過去・現在・未来のつながり、さらには学問どうしのつながりや文化を超えたつながりにまで思考を広げることで、哲学的に考えることがなぜ大切なのかを説き明かす。
目次
序章 哲学的に考えるとはどういうことか
1 哲学的思考に向かって
考えるとはどういうことか
意識の度合い
本能的な動き
植物的な知
受動的な思考と能動的な思考
情念からの離脱
哲学の対象
意識の消失
閉じと開き
能動性への転換
2 つながりをめぐる準備的考察
ヴァーチャルなもの
可能態と現実態
想像力の問題
観察から問題提起へ
創造する哲学
3 本書の構成
哲学とは何か
古典の力
作品という世界
第1章 読むという営み──書物のつながり
1 読解とはどういうことか
文章の相関図
〈つながり〉の前提にあるもの
2 三段階の法則──つながりを解明するための予備的考察
理論の役割
神学的段階
実証性とは何か
原因を想定する
形而上学的段階
失われた〈つながり〉
再構築の試み
実証的段階
3 読むことと創造
説得術としてのレトリック
比喩の役割
レトリックの復権
想像力の位置
〈つながり〉の成立
解釈とは何か
美しさはどこからくるか
連想という関係
階層とアウトライン
4 能動的な読書
図書館のどこにライプニッツはいるか?
主題目録からハイパーテクストへ
パーソナルなデータベース
マルチファイル検索
第2章 網の目のなかの個人──言葉とのつながり
1 生きた言葉と死んだ言葉
言葉の生命
言葉が凝固するとき
古典という結晶
融け出す言葉
つながりが思想を創る
2 言葉が結晶になるとき
思想は目に見えない
小説の誕生
思想のフィードバック
文学的連想のネットワーク
つながりの網の目
3 人間の形成
記録係と判断者
コントの相対主義
第3章 人間らしさとは何か──過去とのつながり、未来とのつながり
1 過去を記念する
動物にとっての過去
社会学の「歴史的方法」
生物学から社会学へ
記念するとはどういうことか
批判から再建へ
記念によってつながる過去
言語と芸術の起源
2 抵抗する言葉
言葉としての対象
思想が創られるとき
3 創造という跳躍
可能性とは何か
可能性の創造
ヴァーチャル化
アクチュアル化
インターフェイスとしてのテクスト
哲学的思考の跳躍力
第4章 科学的であることの意味──学問どうしのつながり
1 何のための科学か
学問という体系
精神的権力と分業
分業の落とし穴
経済学の方法論的個人主義
学問の現代的状況
2 要約の不可能性
科学者という言葉
コントの実証主義哲学
人間的な営み
要約的知識の害悪
祈りという営み
3 諸学問の階層
外からの思考
総体的精神
予見とは何か
数学の教えるもの
知性に基づく推論
天文学の教えるもの
物理学、化学、生物学の教えるもの
科学の階層を登る
4 社会学の方法
厳密性の罠
幼児を観察する
ホモ・エコノミクス
社会学へ
第5章 個人から人類へ──人と人とのつながり
1 人間の営みとしての学問
学者の態度という問題
現実の断罪
数学による「支配」
普遍数学の夢と現実
体系化の学としての哲学
還元主義を超えて
コントの「論理」
百科全書派の功罪
真の百科全書的教養へ
2 個人主義的利己主義からの脱却
個人主義の問い直し
誤りからの目覚め
第七の学問
フェティシズムの回復
3 人類という視点
コントと宗教
絶対的言語と社会
諸芸術のつながり
主観的綜合
社会動学と社会静学
コントの歴史哲学
第6章 共存する思想──文化間のつながり
1 近代とは何か
近代社会と進歩史観
信頼の確立
安易なグローバリズムを超えて
新たな〈つながり〉の可能性
歓待の精神
2 外に出ること
インターネットという客体
ヴァーチャル化と世界
『南の思想』の射程
トランスカルチュラルな文化論
終章 集合的知性へ
人類とヴァーチャル化
誰のものでもない「集合的知性」
社会性と人間らしさ
新たなヒューマニズム
善く生きること
あとがき
文献案内
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
chie@掃溜めのお猿
Ex libris 毒餃子
木麻黄
くらげかも
くまくま
-
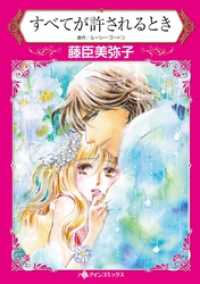
- 電子書籍
- すべてが許されるとき【分冊】 10巻 …
-
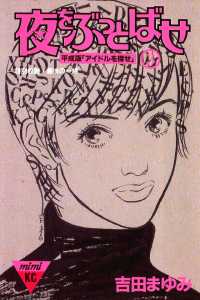
- 電子書籍
- 夜をぶっとばせ(3)
-
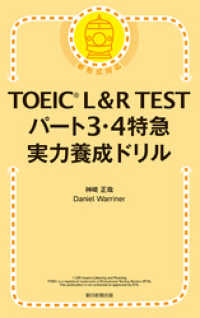
- 電子書籍
- TOEIC L&R TEST パート3…
-

- 電子書籍
- 煉獄に笑う(2) Beatsコミックス
-
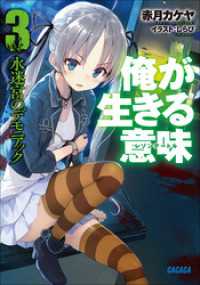
- 電子書籍
- 俺が生きる意味3 水迷宮のデモニアック…




