内容説明
香港の民主化運動への禁圧、台湾への軍事的圧力――。現在の中国が見せる、特に南部への強硬な姿勢には、どのような歴史的背景があるのだろうか。中国史のフロンティア=華南地方の周辺民族と移民活動に焦点を当て、南から中国史を見直す。
中国の歴史は従来、黄河流域に展開した古代王朝の興亡史や、騎馬遊牧民が打ち立てた大帝国など、「北から動く」ものとして捉えられてきた。しかし、清代末期、広州などの港町を窓口とした近代ヨーロッパとの出会いをきっかけに、新しい時代が始まる。洪秀全の太平天国、孫文の辛亥革命など、社会変革の大きな動きは南から起こり、中国史上初めて「南からの風が吹いた」のである。その「風」を起こしたのは、漢民族にヤオ族・チワン族やミャオ族、さらに客家など様々な人々が移動と定住を繰り返す「越境のエネルギー」だった。
世界のチャイナタウンではなぜ広東語が話され、福建省出身者が多いのか。周辺民族は、漢民族のもたらす「文明」にどのように抵抗し、あるいは同化したのか。辺境でこそ過剰になる科挙への情熱や、キリスト教や儒教と軋轢を起こす秘密結社、漢民族から日本人そして国民党と、波状的な支配を受ける台湾原住民など、中国社会の多様性と流動性を史料と現地調査から明らかにし、そこで懸命に生きてきた人々の姿を見つめる。
目次
序章 中国史のフロンティア=華南
第一章 動き出した人々――福建・広東の移民活動
第二章 越境する漢人移民――広西と台湾への入植
第三章 辺境の科挙熱――中国文明と向き合う
第四章 周辺民族の抵抗と漢文化――流入する移民と秘密結社
第五章 太平天国を生んだ村で――移民社会のリーダーたち
第六章 械闘と動乱の時代――つくり直される境界
終章 越境してやまない人々――海外移住と新たな統合
あとがき
参考文献
索引
目次
序章 中国史のフロンティア=華南
第一章 動き出した人々――福建・広東の移民活動
1 福建と広東――華人のふるさと
2 中国の人口爆発と移民活動
第二章 越境する漢人移民――広西と台湾への入植
1 瘴気の地・広西
2 台湾・うるわしの島
3 移民の要因とネットワーク
4 「ワンセック」という行動様式
第三章 辺境の科挙熱――中国文明と向き合う
1 土司の周辺民族統治と改土帰流
2 辺境での科挙受験と儒教
3 あるチワン族一家の「漢化」
第四章 周辺民族の抵抗と漢文化――流入する移民と秘密結社
1 移民の流入と周辺民族の抵抗
2 「漢人化」する周辺民族
3 台湾原住民の世界と日本の統治
第五章 太平天国を生んだ村で――移民社会のリーダーたち
1 移民宗族の台頭と競争
2 新興エリートの「自治」
3 下位集団の上昇戦略――造反か、「軍功」か
第六章 械闘と動乱の時代――つくり直される境界
1 広西の来土械闘
2 広東の土客械闘
3 台湾の分類械闘
終章 越境してやまない人々――海外移住と新たな統合
1 動乱が生んだ移民――アメリカ・日本・台湾
2 華南の移民史と中国の未来
あとがき
参考文献
索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
榊原 香織
サアベドラ
さとうしん
Toska
-
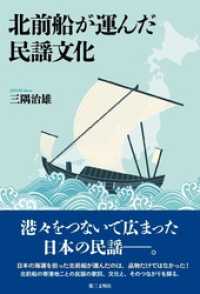
- 電子書籍
- 北前船が運んだ民謡文化
-

- 電子書籍
- たちばなみよこの作ってたのしいフェルト…
-

- 電子書籍
- 【電子版】紅殻のパンドラ(11) 角川…
-

- DVD
- 魁!!極道ヤンキー学園2
-
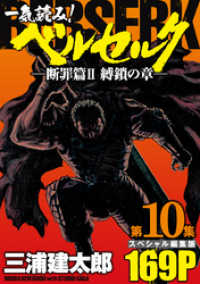
- 電子書籍
- 一気読み!『ベルセルク』スペシャル編集…




