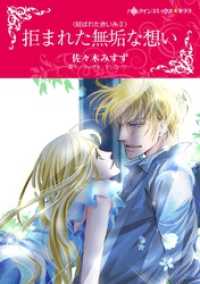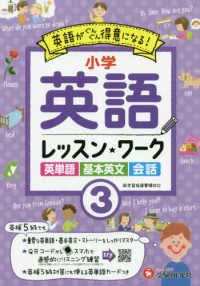- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
世界秩序を生み出した歴史的背景を理解できれば、中国、中東の問題点も見えてくる――。
21世紀の国際秩序のありようを、国際関係論の第一人者が歴史的な観点から読み解く。ロングセラー『外交』に匹敵する名著。
本書は、キッシンジャーの名著『国際秩序』(2016年刊)を上下に分けてビジネス人文庫化するもの。
冷戦時代の枠組みは、アメリカ、ヨーロッパ先進国、ソ連といった限られた地域の国々が参加して作られた制度であった。しかし、冷戦終結後、中国、インド、ブラジルが発言力を強める一方、ロシアは自国の衰退を直視することを拒否し、様々な行動に踏み切っている。
この「真にグローバル化した」国際環境において、どのような「国際秩序」が作られるべきか? いま最も重要な話題にキッシンジャーが挑む。
下巻では、親中派と見なされているキッシンジャーが中国について厳しい評価を示し、アメリカがどのような大国であるべきかを論じる。文庫化にあたって巻末に兼原信克氏(元内閣官房副長官補兼国家安全保障局次長)の解説を掲載。
目次
第6章 アジアの秩序に向けて――対決か協調か?
第7章 「すべての人類のために行動する」――アメリカとその秩序の概念
第8章 アメリカ――矛盾をはらんだ超大国
第9章 テクノロジー、釣り合い、人道意識
結 論 私たちの時代の世界秩序は?
謝辞
訳者あとがき
文庫版 解説(兼原信克)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
TS10
17
下巻では、中国とアメリカ、将来の世界秩序について論じる。ウェストファリア条約以降、ヨーロッパ諸国によって定義された正統性に基づく国際秩序(ウェストファリア・システム)を、グローバルな規模で正統性の均衡を取り直した上で、世界秩序として再構築するべきだというのが本書の要旨だろうか。しかし、インターネット生活の中で育つだろう将来の指導者にその実行が可能か著者は強く憂慮する。後半は抽象的な表現が多く、あまり理解できなかった。上下巻通して定訳を無視した訳語の選択に違和感を覚えたので、いつか原書で再読したい。2024/07/18
Hiroshi
9
下巻はアジアの中国の後にアメリカをセオドア・ルーズベルトから見ていき、テクノロジーの進化とそれによる人間意識の変化を見て21世紀の国際秩序を確認していく。中国は皇帝支配が始まってから朝貢で周辺国を支配していたので、ヴェストファーレン体制の発想がない。毛沢東の共産党になってもその雰囲気があり、それとヴェストファーレン体制の中間の秩序を保っている。アメリカは議会からなる共和国であり自由思想を輸出している。ヨーロッパは秩序システムから道徳の原理を外したが、アメリカには相手の信仰や信念を変えようとする精神がある。2024/03/20
青いランプ
3
キッシンジャーが書くから、どんなことを書くのか、ワクワクして読んだが、彼なりの世界史の理解だった。面白いというより、「へー」という本だった。2023/02/27
ゼロ投資大学
2
世界の警察として地球上のあらゆる場所で国際秩序の形成に関わってきたアメリカ。核兵器の拡散と冷戦の進行によって、国際社会は危ういバランスで均衡が保たれていた。2025/07/10
Shinsuke Mutsukura
0
コイツは、アジアやイスラムについては勉強はしてるが、あまり理解してねぇようだな。自分が優秀だって頭でいるからだろうと思う。Chinaをモンスターにしちまったのも、コイツの所為だから、胸糞が悪くなった。2024/04/24