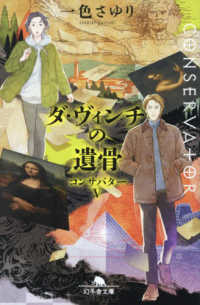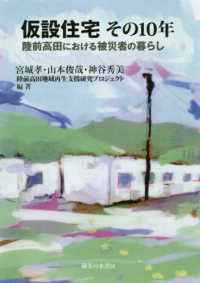内容説明
「生きて帰るまでが撮影です」妖精のミイラ、闇夜に潜むワニ、世界一の星空、国境の壁と移民、反政府ゲリラと最凶のギャング……。中南米で10年以上活動を続けてきた撮影コーディネーターが、日本ではありえないマジカルな実体験の数々を語る。笑いと涙、驚異と感動のノンフィクション!【推薦コメント】国分拓(NHKディレクター、ノンフィクション作家)「無謀ながら謙虚に、大胆かつ繊細に、作者はラテンアメリカの『目を凝らさないと見えない人々』の声を掬い上げていく。読んでいる間ずっと、一緒に旅をしている気持ちになった」/金井真紀(文筆家、イラストレーター)「海外発のルポを愛する同好の士に告ぐ。こんなにディープで軽やかな本はめったにないです。嘉山さんはタダモノじゃないとわかっていたけど、いい本すぎてちょっとずるい」
目次
第1話 UFO大国の妖精のミイラ(メキシコ)
第2話 アマゾン川に沈みゆく船長(コロンビア―ブラジル)
第3話 野菜抜きのトマトレタスバーガー(ベネズエラ)
第4話 星のない東京から、星だらけのアタカマ砂漠へ(チリ)
第5話 2つの地震、上げられた拳(メキシコ)
第6話 ゲリラとお好み焼き(日本―コロンビア)
第7話 壁が分かつ人々(メキシコ)
第8話 彼と彼女たちの夢(メキシコ)
第9話 世界最悪の街、元ギャングと移民家族(ホンジュラス)
第10話 壁を越えるとき(アメリカ―メキシコ)
最終話 コロナ禍の撮影コーディネーター(メキシコ)
-

- 和書
- 神経疾患看護マニュアル