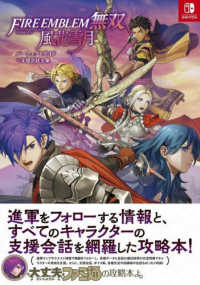内容説明
新出題基準に準拠。最新の知見をもとに関係法規,放射線防護の考え方,被ばく測定と管理,取扱い施設,汚染対策,医療安全を解説。
目次
表紙
本扉
刊行に当たって
はじめに
目次
本書の用語・略語等の記載について
法律用語等と本書で用いた略語の対照表
第1 章放射線関係法規
1.1 放射線防護の歴史と国内外の取組み
1.2 放射線防護に関する日本の主要法規
1.2.1 原子力基本法
1.2.2 原子力規制委員会設置法
1.2.3 放射性同位元素等の規制に関する法律[RI規制法,放射性同位元素等規制法]
1.2.4 医療法
1.2.5 診療放射線技師法[技師法]
1.2.6 医薬品,医療機器等の品質,有効性および安全性の確保等に関する法律[医薬医療機器等法]
1.2.7 労働安全衛生法
1.2.8 国家公務員法/船員保険法
1.3 用語の定義(医療法を軸として)
1.3.1 放射線の定義
1.3.2 放射線源の分類と定義
1.3.3 場所の定義(医療法)
1.3.4 場所の定義(RI規制法)
1.3.5 人の定義と限度(医療法)
1.3.6 人の定義と限度(RI規制法)
1.4 届出(医療法)
1.4.1 届出義務〔医法15-3〕
1.4.2 届出事項
1.5 X線装置等の防護基準(医療法)
1.5.1 X 線装置の防護基準〔医則30-1~5〕
1.5.2 発生装置・粒子線装置の防護基準〔医則30 の2,医則30 の2 の2〕
1.5.3 照射装置の防護基準〔医則30-3〕
1.6 X線診療室等の構造設備基準(医療法)
1.6.1 X 線診療室〔医則30 の4〕
1.6.2 発生装置/粒子線装置使用室〔医則30 の5,30 の5 の2〕
1.6.3 照射装置使用室〔医則30-6〕
1.6.4 照射器具使用室〔医則30 の7〕
1.6.5 装備機器使用室〔医則30 の7 の2〕
1.6.6 診療用RI 使用室〔医則30 の8〕
1.6.7 陽電子RI 使用室〔医則30 の8 の2〕
1.6.8 貯蔵施設〔医則30 の9〕
1.6.9 運搬容器〔医則30 の10〕
1.6.10 廃棄施設〔医則30 の11〕
1.6.11 放射線治療病室〔医則30 の12〕
1.6.12 放射化物保管設備〔R則14 の7(7)の2〕
1.7 管理者の義務(医療法)
1.7.1 注意事項の掲示〔医則30 の13〕
1.7.2 使用の場所等の制限〔医則30 の14〕
1.7.3 診療用放射性同位元素等の廃棄の委託〔医則30 の14 の2〕
1.7.4 患者の入院制限〔医則30 の15〕
1.7.5 管理区域〔医則30 の16〕
1.7.6 敷地の境界等における防護〔医則30 の17〕
1.7.7 放射線診療従事者等の被ばく防止〔医則30 の18〕
1.7.8 患者の被ばく防止〔医則30 の19〕
1.7.9 取扱者の遵守事項〔医則30 の20〕
1.7.10 X 線装置等の測定〔医則30 の21〕
1.7.11 放射線障害が発生するおそれのある場所の測定〔医則30 の22〕
1.7.12 記帳〔医則30 の23〕
1.7.13 廃止後の措置〔医則30 の24〕
1.7.14 事故の場合の措置〔医則30 の25〕
1.8 測定(医療法,RI規制法)
1.8.1 X 線装置等の測定〔医則30 の21〕
1.8.2 場所の測定〔医則30 の22〕
1.8.3 人の測定〔医則30 の18〕
1.8.4 被ばく線量の測定方法及び算定方法(医療法)
1.8.5 人の測定に関する測定結果の作成と保存〔R則20-4〕
1.9 健康診断等(RI規制法,電離則)
1.9.1 RI 規制法による健康診断〔R法23,R 則22〕
1.9.2 放射線障害を受けた者等に対する処置〔R法24,R 則23〕
1.9.3 電離則による健康診断
1.10 教育訓練(RI規制法)
1.11 事故および危険時の措置(RI規制法)
1.12 放射線取扱主任者(RI規制法)
1.12.1 主任者の選任〔R法34,R則30〕
1.12.2 選任の届出等〔R則30〕
1.12.3 取扱主任者の義務等〔R法36〕
1.13 放射線障害予防規定(RI規制法)
1.14 診療放射線技師法
1.14.1 診療放射線技師とは
1.14.2 免許・技師籍等
1.14.3 診療放射線技師の業務等[技法24 の2,技令17,技則15-2]
演習問題
第2 章放射線防護の基本概念
2.1 放射線防護と放射線管理
2.2 ICRPの基本勧告
2.3 放射線被ばくの種類
2.3.1 放射線源による分類
2.3.2 被ばくの内容による分類
2.3.3 被ばくの形態による分類
2.4 放射線被ばくによる人体への影響
2.4.1 身体的影響と遺伝的影響
2.4.2 確率的影響と確定的影響
2.4.3 急性障害と晩発障害
2.5 放射線防護に用いられる諸量
2.5.1 物理量
2.5.2 防護量
2.6 放射線防護の基本的な考え方
2.6.1 放射線防護の目的
2.6.2 放射線防護体系の三原則
2.6.3 行為と介入
2.6.4 被ばく状況による分類
2.6.5 線量拘束値と参考レベル
2.6.6 線量限度
2.6.7 患者の医療被ばくにおける放射線防護の考え方
2.6.8 診断参考レベル
2.7 診療用放射線に係る安全管理体制
2.7.1 診療用放射線に係る安全管理のための責任者の配置
2.7.2 診療用放射線の安全利用のための指針の策定
2.7.3 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施
2.7.4 放射線診療を受ける者の被ばく線量の管理および記録
2.7.5 診療用放射線に関する情報などの収集と報告
2.8 職業被ばくに対する防護
2.8.1 外部被ばくに対する防護
2.8.2 放射線の種類と遮へいの考え方
2.8.3 内部被ばくに対する防護
演習問題
第3 章個人の被ばく測定と施設環境測定
3.1 放射線管理のための測定
3.2 放射線管理に用いられる量
3.2.1 実用量と防護量
3.2.2 線量当量
3.2.3 外部被ばくの実用量
3.2.4 実用量と法令における測定量との関係
3.2.5 放射線場の量からの換算係数
3.2.6 内部被ばく
3.3 外部被ばく線量の測定
3.3.1 個人線量計の概要
3.3.2 個人線量計の特徴と特性
3.3.3 測定方法と結果の評価
3.4 内部被ばく線量の測定
3.4.1 モニタリングの概要
3.4.2 実効線量係数
3.4.3 体内放射能の測定方法の概要
3.4.4 内部被ばくの測定と評価
3.5 個人被ばく線量の記録と保存
3.6 施設・環境の線量測定
3.6.1 管理区域におけるモニタリングの概要
3.6.2 測定器の種類と測定の方法
3.6.3 外部放射線の測定と評価
3.7 測定器の保守管理
3.7.1 校正の概要
3.7.2 校正の種類と方法
3.7.3 実用測定器の簡素化した校正
3.7.4 実用測定器の機能確認
3.7.5 測定された値の不確かさ
演習問題
第4 章放射線取扱施設の管理
4.1 施設設計の考え方
4.1.1 X 線診療室
4.1.2 密封線源を使用する施設
4.1.3 非密封線源を使用する施設
4.1.4 発生装置/粒子線装置使用室
4.2 施設の遮へい計算
4.2.1 X 線診療室の画壁等の実効線量の算定
4.2.2 密封線源
4.2.3 高エネルギー放射線発生装置
4.3 排気・排水設備の構造と能力
4.3.1 核医学施設における排気・排水設備
4.3.2 排気設備の構造
4.3.3 排水設備の構造
4.4 放射線取扱施設の安全管理
4.4.1 教育訓練
4.4.2 測定および記帳・記録
4.4.3 特定放射性同位元素(特定RI)
4.4.4 放射化物の取扱い
4.4.5 汚染対策,汚染除去
演習問題
第5 章放射線管理の方法と事故対応
5.1 線源の管理
5.1.1 診療用線源の分類
5.1.2 線源の安全取扱いの概要
5.1.3 診療用発生装置の安全取扱い
5.1.4 密封線源の安全取扱い
5.1.5 非密封線源の安全取扱い
5.1.6 外部被ばくの防護
5.1.7 線源(容器を含む)の汚染対策
5.2 表面汚染管理
5.2.1 表面汚染の概要
5.2.2 表面汚染密度の測定
5.2.3 結果の評価(表面汚染密度の計算)
5.2.4 汚染対策
5.2.5 除染の実際
5.3 放射性廃棄物
5.3.1 分類と処理法
5.3.2 廃棄の方法
5.3.3 特殊な医療廃棄物とRI 内用療法を受けた患者の退出
5.3.4 放射化物の放射線管理
5.3.5 濃度確認[R 法33 の2]
5.4 放射線事故
5.4.1 事故事例
5.4.2 事故・緊急事態の一般的な分類
5.4.3 事故および危険時の措置
5.4.4 緊急作業
5.4.5 緊急時の措置の詳細
5.4.6 緊急被ばく医療
演習問題
演習問題解答
索引
著者紹介
奥付
-

- 電子書籍
- 至急花嫁求む【分冊】 3巻 ハーレクイ…
-
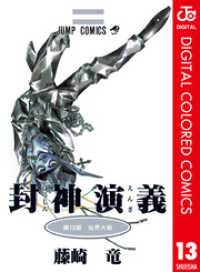
- 電子書籍
- 封神演義 カラー版 13 ジャンプコミ…