内容説明
奴隷制時代から南北戦争、公民権運動をへて真の解放をめざす現代まで。アメリカ黒人の歴史とは、壮絶な差別との闘いであり、その反骨の精神はとりわけ音楽の形で表現されてきた。しかし黒人音楽といえば、そのリズムやグルーヴが注目された反面、忘れ去られたのは知性・暗号・超絶技巧という真髄である。今こそ「静かなやり方で」(M・デイヴィス)、新しい歴史を紡ごう。本書は黒人霊歌からブルース、ジャズ、ファンク、ホラーコア、ヒップホップまで、黒人音楽の精神史をひもとき、驚異と奇想の世界へと読者をいざなう。古今東西の文献を博捜した筆者がおくる、新たな黒人音楽史。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たまきら
43
ディープで、主観たっぷり。説明が上手な読み友さんの「狂気じみている」という感想が気になって手に取ったんですが、この本はディープな文化沼にどっぷりはまった者と外から眺めている者という立場の違いでとらえ方が変わってくると思います。自分は東部に住んでいたので西部や南部のアフリカ系の子に出会う機会は大学に行くまでありませんでした。差別や教育格差、ホント全てがカルチャーショックだったなあ。あと最初にオールブラックチャーチに行ったときの驚きといったら…。音楽だけでおさまらないディープな宇宙があるんだよな~。2023/02/27
内島菫
17
私は錯覚や勘違い間違いわざと等を含めて、一見かけ離れているように見えるものをつなぐ直感、本書で言えば「天啓」の蛇行運動にいつもわくわくしてしまう。つなぎ、つながった瞬間は、どこか「始まり」に似ていないだろうか。そして「始まり」にはすべてが綜合されている。本書全体がまさにそうした「始まり」の塊だ。今自分のいる世界がなぜどのようにこうなっているのかを、時間と空間の両軸から縦横無尽につなぎあわせ組み立てる手つきは、まさに「天啓」による神の手のなせる業ではないだろうか(人はたぶんみんな自分の「天啓」と2022/12/13
owlsoul
11
黒人音楽といえば、その身体性から生まれるプリミティブなリズムが想起される。また、アメリカ黒人による表現となれば、それは差別の歴史と切り離すことが出来ず、ゆえに政治的な読み解きが主流となる。本書はそんな一般的な批評軸をあえてずらし、澁澤龍彦や種村季弘を想わせるような、驚異と奇想の世界を黒人音楽史に見いだそうとする。正直、その試みは知的遊戯感が強く、本書から新しい着想を得られるか、単なるでたらめと感じるかは読者次第だろう。ただ、本書を『黒人音楽史』と名付ける商魂に対しては、強い違和感があると言わざるを得ない。2024/01/02
ゆうきなかもと
6
音楽史ではない。題名が悪いと思う。内容はアメリカの黒人音楽の評論であり、極めてマニアックだと思う。面白かったのは、ジョージ・クリントンが『ギバップザファンク』を思いついたのは、デビットボウイの『フェイム』を聴いたからであり、そのボウイもJBの影響を受け、その曲を作ったというところ。さらに面白いのが、ギバップザファンクを聴いてJBも『ホット』という曲を書いたというところ。あと、ビートルズとかディランの影響をジョージ・クリントンが受けていたのも知らなかった。批評部分も素晴らしいが。真実は批評よりも奇なり。2023/04/26
Masaaki Kawai
6
アフロマニエリスムという独自のテーマを設定し論じる、これは論文やった。なので、引用とか連想する事柄の知識量がすごい。帯でいとうせいこうが博覧狂気と書いてるけれど、まさにその通り、過剰で狂気じみてる。そんな本なので一般ウケはしなさそうやけど、たくさんの引用で知識を増やすことができました。2022/12/31
-

- 電子書籍
- 転生したら王女様になりました83話【タ…
-
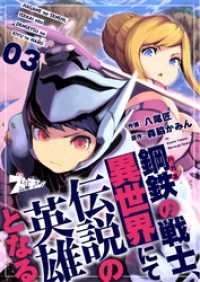
- 電子書籍
- 鋼鉄(ハガネ)の戦士、異世界にて伝説の…
-
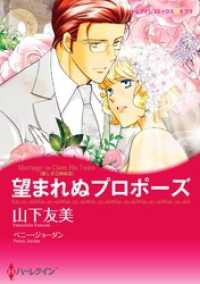
- 電子書籍
- 望まれぬプロポーズ〈麗しき三姉妹III…
-
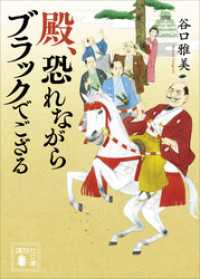
- 電子書籍
- 殿、恐れながらブラックでござる 講談社…
-
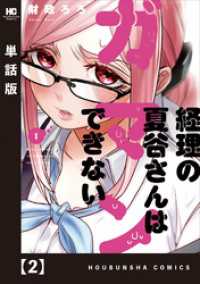
- 電子書籍
- 経理の夏谷さんはガマンできない【単話版…




